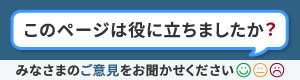神戸市区要保護児童対策地域協議会
最終更新日:2025年8月20日
ページID:74828
ここから本文です。
要保護児童対策地域議会とは
虐待を受けているこどもを始めとする支援対象児童等の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関等がそのこども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です。
このような多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制の明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要であり、このような背景を踏まえ、平成16年に児童福祉法が改正され、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会(以下「要対協」という。)が法的に位置づけられました。
支援対象者
- 児童福祉法第6条の3第8項に規定する「要保護児童(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童)」及びその保護者
- 児童福祉法第6条の3第5項に規定する「要支援児童(保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童に該当するものを除く。))」及びその保護者
- 児童福祉法第6条の3第5項に規定する「特定妊婦(出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦)」
なお、上記1~3を総称して「支援対象児童等」と言います。
要保護児童対策地域協議会の調整機関
各区要保護児童対策地域協議会の調整機関は、区こども家庭支援室(事務局)となります。
各区こども家庭支援室(事務局)の連絡先は以下からご覧ください。
こども家庭支援室について
要保護児童対策地域協議会の機能
業務内容
要対協は、支援対象児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行います(児童福祉法第25条の2第2項)。
神戸市区要保護児童対策地域協議会の構成(三層構造)
代表者会議
要対協の構成員の代表者による会議であり、実際の担当者で構成される実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に1~2回程度開催されます。
実務者会議
実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議における協議事項としては例えば次のようなものが挙げられます。
-
- すべてのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直し等
- 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
- 支援対象児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握
- 要保護児童対策を推進するための啓発活動
- 要対協の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
個別ケース検討会議
個別の支援対象児童等について、直接関わりを有している担当者や今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者により、当該支援対象児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催されます。
要保護児童対策地域協議会の協力要請
支援対象児童等に関する情報の交換や支援の内容に関する協議を行うために必要があると認めるとき、要対協は、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができ、関係機関等は、これに応ずるよう努めなければならないこととされています(児童福祉法第25条の3第1項及び第2項)。
守秘義務
要対協における支援対象児童等に関する情報の共有は、支援対象児童等の適切な保護又は支援を図るためのものであり、要対協の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、要対協の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(児童福祉法第25条の5)。
神戸市各区要対協要綱
- 神戸市東灘区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:671KB)
- 神戸市灘区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:258KB)
- 神戸市中央区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:257KB)
- 神戸市兵庫区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:265KB)
- 神戸市北区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:269KB)
- 神戸市須磨区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:266KB)
- 神戸市長田区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:690KB)
- 神戸市北神区役所要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:657KB)
- 神戸市垂水区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:260KB)
- 神戸市西区要保護児童対策地域協議会設置運営要綱(PDF:258KB)
神戸市区要対協マニュアル
神戸市区要対協についてのマニュアルは以下よりご確認ください。
神戸市区要保護児童対策地域協議会マニュアル(PDF:1,981KB)