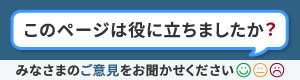小松副市長会見 2025年11月17日
最終更新日:2025年11月20日
ページID:82278
ここから本文です。
・空き家活用と教育を融合した"学住一体型"地域活性化モデルの取組 ~坂のまちエリアリノベーション~
会見資料はこちら(PDF:3,634KB)
空き家活用と教育を融合した“学住一体型”地域活性化モデルの取組 ~坂のまちエリアリノベーション~
司会:
それでは、ただいまから、株式会社CHINTAI並びに株式会社RePlayceとの共同会見のほうを開始したいと思います。
まず最初に、登壇者の方の紹介をしたいと思います。向かって左から御紹介したいと思います。
株式会社CHINTAIより奥田倫也代表取締役社長でございます。
株式会社RePlayceより山本将裕代表取締役CEO、
神戸市、小松恵一副市長でございます。
それでは、初めに、副市長より御挨拶と取組についての御説明のほうをさせていただきます。よろしくお願いします。
小松副市長:
本日は、神戸市が2025年度から取組を開始しました坂のまちエリアリノベーション事業の新たな取組と展開としまして、空き家活用と教育を融合した学住一体型の地域活性化モデルの取組につきまして、株式会社CHINTAI様、それから株式会社RePlayce様との共同会見を開かせていただきます。
本日は、先ほど御紹介ありましたけれども、株式会社CHINTAI様の奥田倫也代表取締役社長と、それから株式会社RePlayceの山本将裕代表取締役CEOの御同席の下、このようなよいニュースを皆様にお届けできることになって、この場をお借りしてこの両者2者の方々に感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。
神戸市では、坂が多い地形を生かしまして、まちの再生やブランド力の向上につなげるために、2024年度より坂のまち神戸プロジェクトを始動し、坂道に関するフォトコンテストや坂に関しての意見交換をするサミットやトークイベントなどを実施してきております。2025年度の取組の第1弾としましては、坂アンバサダーを5組任命しまして、坂を生かした企画イベントの実施や、坂の魅力発信に取り組んでいただいておりまして、7月からは第2弾としまして坂のまちエリアリノベーション事業の取組を開始しているところでございます。
坂の多いエリアにおきましては、平地に比べまして、空き家の解体や建て替えが進みにくいといった現状がございます。まずは、市内の5エリア、黄色い丸数字で表してございますが、こういった5エリアを指定しまして、空き家リノベーションや空き地活用の補助、空き家・空き地関連補助金の要件の一部緩和など、民間事業者の取組の支援を開始しているところでございます。民間事業者様による空き家・空き地の面的な活用を支援することで、地域資源を生かした坂のまちの魅力向上を図り、地域の活性化やエリア価値の向上につなげていきたいと考えてございます。
これまでの空き家活用の取組につきましては、市内事業者様から申請が多かったところではございますが、このたび、このように市外から通信制高校サポート校HR高等学院を運営する株式会社RePlayce様、住宅情報を豊富に持つ株式会社CHINTAI様の2者が、空き家・空き地の利活用という地域課題の解決に向けて、本市でモデル的な取組をしていただけることとなりました。詳細は後ほど両者のほうから御説明いただく予定ではございますが、株式会社RePlayce様の運営するHR高等学院の関西初となる神戸校の、神戸・新開地エリアでの開校を契機に、株式会社CHINTAI様とも連携し、空き家・空き地の利活用を題材としました先行プログラム等を取り組んでいただくこととなっております。
また、坂のまちエリアリノベーション事業の指定エリアにおきまして、神戸電鉄鵯越(駅)周辺におきまして、空き家を活用した学生寮の整備を計画していただいており、本市としましても、両者と連携しながら、空き家の利活用促進に取り組んでいきたいと考えてございます。
さらに、CHINTAI様におかれましては、高校生が自立した暮らしや地域社会への理解を深めるきっかけとなる教材を全国で初めて地域版として作成していただく予定となってございます。
今後の展望ですが、この取組は、産官学の連携により、教育的視点で空き家などの地域課題に取り組む学住一体型のモデルを目指してございます。HR高等学院神戸校をフィールドに、若い視点を生かした企画実行を通じて、実践型の住教育の充実や、将来的に市内で活躍する人材育成に期待しており、坂の多い他のエリアへの展開も見据えて、3者で連携して取り組んでいきたいと考えています。
神戸市としましては、今後もこのような取組のように、民間のアイデア、ノウハウを積極的に取り入れまして、教育を通じた地域課題の解決や、様々なアプローチにより、坂のまちをはじめ、市内の空き家・空き地の活用や地域の魅力向上に積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。
神戸市からは以上です。
司会:
それでは、続きまして、株式会社RePlayce山本CEOよりお話を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。
山本代表取締役CEO:
RePlayce山本です。よろしくお願いします。
まず、簡単に弊社の御紹介させていただければなと思っていまして、弊社ですが、去年4月にNTTドコモからスピンアウトした、いわゆる教育事業をやっておるスタートアップと呼ばれるものになっております。いわゆる投資家さんから出資をいただいて運営している企業体になっております。
続きまして、弊社なんですけども、教育のいわゆる探究教育だったりキャリア教育とかアントレ教育の教材なんかを開発させていただきながら、自社でのスクールという形で、はたらく部という放課後のスクールと、HR高等学院、この4月に代々木で開校しておりまして、代々木で今もう84名ですか、生徒がおりまして、もうぱんぱんになっていますので、来年4月から渋谷、横浜、成城でも開校する予定でおります。いわゆる民間が運営する通信制サポート校というような形のスキームになっておりまして、ただ、今回神戸もまだ認可申請前ではございますので、あくまでこれからどんどん展開していく中で申請もしていきたいなというふうに考えております。
弊社、コンテンツも様々自治体様とかにも御提供させていただいたりもしておりまして、今回、まさに空き家だったりですとか、どう地域を活性化するというところに、いわゆる若年層の知見だったりですとか行動力というところを生かしていくような、何かそんな取組ができたらいいなというふうに考えております。
今、これから新規開校ということで、神戸校というような形で開校していくというような形で、神戸・新開地エリアでの物件というところで、まだこちらも校舎候補地ではあったりするんですけども、今、選定のほうをさせていただいているというような形でございます。まさに今回、神戸市様のいかに地域のリソースを活用して地域をどんどん活性化できるかというところに寄与できる、何かそういった取組に我々としても目指していけたらなというふうに考えております。
今回、いわゆる地域課題解決プログラムということで、弊社、PBLというプロジェクトベースドラーニングと呼ばれる課題解決型のプログラムというのを学校の中でも取り入れさせていただいておりまして、今までもドコモさんだったりMIXIさんとか様々な企業様と連携させていただいております。今回、CHINTAI様とも連携させていただいて、空き家の、まさに地域課題なんかも学生と一緒に解決していきながら、場合によっては空き家を利活用していくというような、そういった取組なんかも御一緒できたらなというふうに考えています。スケジュールでございますが、今回の本連携の開始を皮切りに、より詳細に事業のほうを進めていけたらなというふうに考えております。今、これはもちろん認可申請前なのであくまで予定ではあったりするんですが、2027年4月に開校を目指して取組を進めていけたらなというところで考えております。
弊社からの説明は一旦以上になります。
司会:
ありがとうございました。続きまして、株式会社CHINTAI、奥田社長よりお話をいただきます。よろしくお願いいたします。
奥田代表取締役社長:
改めまして、皆様こんにちは。株式会社CHINTAI、奥田でございます。このたび、このような産官学連携に御一緒できること、大変光栄に存じます。
私どもCHINTAIのほうでは、業界初の賃貸住宅情報誌、こちらの『賃貸住宅ニュース』を発刊して今年で50周年を迎えるというような出版社でございます。業界に新しい価値をつくり続ける、お部屋探しのリーディングカンパニーとして、誰もが自由で「自分らしい暮らし」が実現できる、そんなサービスを展開しておる会社でございます。
現在、賃貸情報を届けるというミッションに加えまして、「社会貢献プロジェクト」と題しまして、地域に根差し、まちづくりの一端を担う存在でありたいという思いから、2024年にこちらのプロジェクトを立ち上げております。本年度は、こちらに書かせていただいている形で、「未来へつなぐ」というテーマの基で、全てで5つの視点から地域もしくは次世代のために取組を進めております。神戸においては、昨年度より神戸市立王子動物園、本年度よりは神戸動物王国に対しまして、動物の種の保全を目的とした支援を実施しております。本連携におきましても、神戸市という地域と生徒の皆さんの未来をつなぐ、そんなかけ橋となれたらいいなというふうに考えておりまして、こちらに対して真摯に取り組んでまいれたらなというふうに思っております。
こちらでは、さらになんですけども、未来へつなぐ取組としまして、先ほど副市長のほうから御説明いただきましたけれども、学生の自立と成長を支援する学生プロジェクトがございます。その中で、成年年齢の引下げ、こちらが2022年に実施されましたけれども、若年層の中でも、賃貸借契約のトラブルが増加しておるということを受けまして、自立をする際に必要な基礎知識を副教材にまとめまして、高校の家庭科授業、こちらを通して届ける取組を現在行っていると。数にすると、今、全国1,000校以上という形の学校で提供しております。さらに、進学などで新生活を始める学生に向けてガクサポというサービスを提供しておりまして、こちらは、学生の新生活への不安に寄り添い、支援するという弊社の思いに賛同いただきました企業様から様々な商品を御提供いただきまして、引っ越しお祝いボックスということで、引っ越しの直後に何か役に立つ、そんなものを詰めたボックスをお送りする取組を推進しています。
今回の連携では、弊社の取組として、これまで全国共通版として作成しておりました副教材、こちらを地域版という形で兵庫・神戸版を作成する予定でございます。地域版は、こちら全国初の取組になります。内容につきましては、今後、神戸市との対話を重ねていく予定でございますが、神戸市はじめ、兵庫県内に密着したハザードマップはじめ、地域の家賃の相場、または主要エリアの特徴や地域の暮らしに密着した情報、こういったものを盛り込みました、地域に根差す兵庫・神戸ならではの住教育、こちらを実現いたしまして、市内及び県内全ての高校での活用を目指しまして、高校生の皆様から暮らしを自分事として捉え、安心安全な住まいの選び、または将来設計を学ぶ機会につなげていけたらというふうに思っております。
さらに、地域社会が抱えます課題を題材に、生徒が自ら考え、解決策を導き出す実践型の学び、こちらをHR高等学院様と共同で構築してまいります。最優先事項の課題としましては、神戸市が直面している空き家問題、特に坂の多い地域に点在いたします空き家・空き地、こちらを対象に、テーマに応じた現地調査、課題の整理、そして活用方法の企画、提案まで一貫して学ぶプログラムを展開してまいります。生徒の皆さんが地域住民、行政職員、不動産会社との対話を重ねて、自身が考える空き家活用の取組、こちらを通じて、地域活性化の在り方を模索していく、そんなプログラムになります。CHINTAIはこうした取組を通じまして、若い世代が自分たちのまちを考えて行動に移していくきっかけをつくっていきたいと考えております。
以上です。
質疑応答
記者:
今回の発表は、このHR高等学院で空き家をテーマにした、今度開校される高等学院で空き家をテーマにした教育プログラムを生徒に提供することに対して、神戸市とCHINTAIさんが関わっていかれるということなんでしょうか。いま一つ、皆さんがいろんなことをするという発表で、誰がどうするかというのが、もう一つ分かりにくいので整理していただけたらと思うんですけど。
小松副市長:
神戸市、やはり人口減少社会にあって、人口が減っていく中でも神戸市の特性を生かした住みよいまちづくりをやっていくというのを今、様々な施策を取り組んでいます。そういった中で、この空き家・空き地というのは、対症療法的な事業でやっていることが多くて、なかなか所有者とか関係者だけと行政が一緒に考えていくみたいな場面はあったんですけれども、ここにより多くの方、特にこの産官学、こういったところが連携して様々なアイデアなりノウハウを入れながら、そういった空き家・空き地の活用に取り組んでいきたいと考えて、まずは全国的に、先ほども申し上げましたが、市内の事業者様の申請が多かったんですが、今回様々な市の都市局なり建設局なり建築住宅局なり様々な部署が連携して、市外の事業者様にもお声かけして、今回、RePlayce様は、新開地に学校を開設していただくということで、学住の学、それから住のほうはCHINTAI様のほうがこういった学生の方々の寮を、これはまだ今プランニングの段階ですが、寮を空き家活用でリノベーションできたらということで考えていただいています。こういったことで、産官学が連携して、まさに教育という新たな分野を通じたこの空き家活用ということですので、国内でどこかでやられているかどうか私もよく分かりませんけれども、こういった新たな取組を神戸市がしていくということで、この3者で今日はこの事業内容の説明をさせていただいたという状況でございます。
記者:
ありがとうございます。HR高等学院は、既に1校開校しているということですか。
山本代表取締役CEO:
そうですね。代々木に今、校舎を開校しておりまして、来年の4月から渋谷と横浜と成城でも開校する予定になっています。
記者:
26年以降3つのキャンパスを新設予定というのは、これは来年度の話。
山本代表取締役CEO:
そうですね、来年度の話になっています。
記者:
26年度時点で計4校になるということですね。
山本代表取締役CEO:
そうですね。
記者:
じゃ、神戸校と言っていいんですか。
山本代表取締役CEO:
そうですね。我々自身も関西に進出したいというのがあった中で、今回、神戸市さんと御一緒することで、神戸を拠点として関西での進出をしていきたいなというところを考えております。
記者:
神戸校で5校目になるという解釈でいいですか。
山本代表取締役CEO:
はい、5校目になります。弊社の代々木の校舎もそうなんですけど、今も地方からわざわざ引っ越して、独り暮らしして通っている子とかもいたりするんですね。なので、一定、集客力も含めてですけども、ありますので、ある意味、地域に人が来るというきっかけを、弊社のプラットフォームを活用して実現できたらなというふうに考えております。
記者:
HR高等学院さんは通信制高校?
山本代表取締役CEO:
通信制サポート校と呼ばれるものでありまして、トライ式高等学院さんとかと同じスキームなんですけど、通信制高校と提携することで、高卒の単位も取りながら、我々自身はオルタナティブな学びの提供をするというものになっておりまして、高卒の単位を取りながらビジネスの教育だったり課題解決能力を養っていくみたいな話。先ほど言ったアントレ教育とか探究教育とかキャリア教育とか、そういったことを大事にしている学校になっております。
記者:
じゃ、純粋な通信制高校ではなくて、通いもあるような。基本的には通学すると。
山本代表取締役CEO:
通学メインですね。弊社の場合、今、代々木で7割が通学しておりまして、3割がフルオンラインで、オンラインでも通学。バーチャル空間に校舎があって、そこに通学している形なんですけども。なので、基本的には通学するという前提での通信の形を取ってます。
記者:
で、今回のプログラムは教育課程の一環としてと言ってもいいんですか。
山本代表取締役CEO:
そうですね。まさに教育の一環として、これから地域で根差して学生たちが活躍していくというのは多分、地域社会において必須の取組かなというふうに思っておりまして、我々としても、もちろん今、企業との連携はしていますけども、こういった自治体様と御一緒させていただきながら、そういった機会をちゃんとつくっていくということが実現できたらなというところで今回、神戸市さんと御一緒させていただいたというような形です。
記者:
では、HR高等学院の教育活動の一環として、空き家の解消という課題解決に授業で取り組むということでしょうか。
山本代表取締役CEO:
そうですね。授業で取り組むということもこれからつくっていきたいなというふうには思っております。
記者:
それは単位も取れるような。
山本代表取締役CEO:
いや、あくまで単位は算数、国語、理科、社会が中心にはなりますので、単位というよりは、いわゆる課外活動的な形での、HR高等学院のプログラムとしてそういったことをやっていくというような形でございます。
記者:
HR高等学院は新開地、これはもう決定?
山本代表取締役CEO:
まだ候補の1つというような形ではございまして、今、物件のほうを様々検討している中で、1つ優良候補として、物件としては考えているというような形でございます。
記者:
じゃ、神戸市内の都市部になるのかな。神戸市内、新開地というのを方針として今のところ考えていらっしゃって。
山本代表取締役CEO:
そうですね。神戸・新開地エリアということで今考えさせていただいておりまして、ただ、これも神戸市さんの空き家の活用だったりですとか、そういったところとひもづけられる、何かそんな文脈になれる場所かどうかも大事かなと思っていますので、そのあたりも神戸市さんと議論させていただきながら決めたいなと思っています。
記者:
教育活動として空き家の課題解決に取り組まれるという、どの辺りのどの空き家でとか、そういうところまではまだ決まっていないですか。開校がまだ先なので、まだだと思いますけども。
山本代表取締役CEO:
そうですね、そこもこれから神戸市さんと一緒に詰めていきながら、実際の場所だったりですとか、そういったところは選定できたらなというふうには思ってます。
記者:
それは指導者というか、先生というか、そういう講師側の方はどういう方を想定していらっしゃるんですか。
山本代表取締役CEO:
我々は民間の形になるので、教職免許を持った人というよりは、我々で今も社員で抱えているメンバーがいるんですけども、いわゆるビジネスパーソンとしてそういう課題解決能力だったりですとか、そういったことをレクチャーできる人間を我々が育成しておりますので、そういった人をきちんと現場に配置する予定です。
記者:
CHINTAIさんにお伺いしたいんですが、この兵庫・神戸版の副教材ですけど、これは今回のプログラムというよりは、あまねく兵庫県内の高校生のためにつくるというようなイメージでしょうか。
奥田代表取締役社長:
いえ、というよりは今回のプロジェクトありきだと思っていて、神戸市様との対話の中で、神戸を中心とした地域版の作成をしてもらえると助かるというか、一緒にそういったものをつくりたいというお声を頂戴しましたので、作成すると。なので、基本的に他のエリアで作成するという予定は、今のところはないです。現状、神戸だけの予定です。
記者:
神戸市内の高校生に使ってもらうというイメージ。
奥田代表取締役社長:
願わくは兵庫県内全てにおいて使っていただけたらなというふうに思っているんですけど、ベースとしては、神戸市内が基本的にベースと考えています。
記者:
それ、希望する学校に配布するようなのですか。
奥田代表取締役社長:
そうですね。家庭科の先生から御希望をいただいた先には無料で提供するという予定でおります。ただただ受け身で待つということでもなくて、家庭科の先生方が集まる勉強会ですとか、私学においては私学協会様と連携をしながら、こういったものをつくります、もしくは導入しませんかという試みはCHINTAIのほうからでも促していきたいと思っています。
記者:
あと、この「教育×空き家活用」プログラムなんですけど、これはHR高等学院さんの教育で使うという意味合いでしょうか。
奥田代表取締役社長:
そうですね。共同で、プロジェクトとして授業をつくっていく、そんな形で考えてます。
記者:
じゃ、先ほど来お伺いしているHR高等学院さんの課外活動での空き家解消のプログラムに、CHINTAIさんがプログラム開発という形で関わっていかれるというような感じですか。
奥田代表取締役社長:
そうですね。私どもが持っている住環境に対する情報などを活用いただきながら推し進めていくプロジェクトです。
記者:
小松副市長にお伺いしますけど、その上で、その2社に対して、神戸市としてどういうふうな形で関わっていかれたいかというのを、もし具体的にあればお願いしたいんですけれども。
小松副市長:
今、坂のまちエリアリノベーション事業に補助というのがございまして、その空き家活用などがありまして、各種補助金などの支援施策を持ってございます。こういったものを踏まえまして、この2社の方々がされる事業の事業スキーム等をいろいろ整理させていただきながら、そういった補助ができる、該当するものがあれば神戸市として積極的に支援をしていきたいと考えてます。
それ以外に、やはりこういった事業をやるには、地域の情報というか、そういった我々が持っている情報も重要だと思いますので、この辺も提供させていただきながら、空き家の活用という意味ではマッチングみたいなところを3者で連携して取り組んでいきたいと考えてます。
記者:
空き家なので、所有者が基本的にはいると思うんですけど、どういう空き家を使っていくかというのがそんなに簡単じゃないのかなと思うんですけど、そのあたりはどういうふうに。神戸市がその辺は調整される予定なんですかね。
小松副市長:
先ほども申し上げましたけど、我々がそういった地域情報を持っていますので、この両者様が計画するプランニングに応じて、どういったものを空き家として求めておられるかというのを把握して、それへのマッチングをしていきたいと考えています。
記者:
この空き家活用促進補助というのは、そういった空き家活用のときに補助できるようなメニューになっているんですかね。支援制度のところなんですけど、今、この2者が進めようとされていらっしゃるプログラムに対して補助できるかもしれないということなんですかね。
小松副市長:
そうですね。補助金はたくさんありまして、例えば空き家活用応援制度であったり、維持の費用の補助であったり、初期費用の補助であったり、あと、建築家との協働による空き家利活用促進補助であったりとか、老朽家屋のそういった解体等の補助であったり、いろんな補助がありますので、事業内容に応じて、それを使えるもの、事業スキームを把握しながら、それを使えるもので支援をさせていただきたいと考えています。
記者:
小松副市長とCHINTAIさんにお伺いするんですけど、この「一人暮らしガイド」なんですけど、先ほどこの事業に絡む形でやっていきたいというお話だったんですけども、神戸市としてはやっぱり若い方が市外に流出してしまうという状況とかから、市内で探してほしいというところを受けてなのかということと、CHINTAIさんとしては、空き家というところまでは分からないけど、やっぱり神戸市内で物件探ししてもらうのに活用していただけるようにというところでお互いの利害が一致したという認識で合っていますかという質問です。
小松副市長:
神戸市内にお住まいの、例えば高校生の方が、大学とかこういった学校に進学される際に、一人暮らしされるケースもあるでしょうが、市内の方は、多分、おおむね自宅から通学される方が多いと思いますので、どちらかというと、市外なり県内から神戸市に来ていただく学生様、高校生様とかがこういったCHINTAI様の情報とかを把握しながら、より学生様に神戸を選んでいただけるような支援策としてこういったことを進めていきたいなと考えています。
記者:
奥田様、何か付け足すことがありましたら。特にないですか。
奥田代表取締役社長:
1点確認なんですけど、ここって今、副教材の部分を聞いていただいている形ですかね。
記者:
私がお聞きしたのはこの「一人暮らしガイド」についてです。
奥田代表取締役社長:
そうですね。ありがとうございます。ここで付け加えるというと、CHINTAI自体、全国共通版でそもそも作成をしていますと。ただ、一方で、その地域に応じた特徴というものがやっぱりそこに存在しないと、例えば神戸の人が東京だとかの家賃相場を見て部屋探しの情報に興味関心を持って取り組んでいただけるかというと、そうではないというふうなのがもともと課題感として持ち合わせていました。なぜ今回地域版を作成するかというところでいけば、そもそも神戸の方々あるいは高校生の方々に対して、今、賃貸借契約のトラブルに巻き込まれるケースというのが全国的に増えていて、これが神戸においては少なくなってほしいですし、じゃ、どうしたら少なくなるかというのが、やはりきちっと正しい知識を持って、部屋探しの際に迷わず安心してスタートいただける、その手助けはCHINTAIができるなというふうに考えておりますので、神戸市と協力の下、地域に特化した情報を入れ込んだものをつくり、皆様の一人暮らし、これが市外もしくは県外になる可能性もありますけど、例えばですけど、神戸で学んだ、もしくは神戸市としたプロジェクトがしっかり自分たちのためになっているなというふうなところを実感いただけると、それはCHINTAIとして好ましいかなと思っております。
記者:
3者が連携することによって何が生まれるかのイメージをもう少し伺いたくて、今までも神戸市は空き家に対する先駆的な取組をやっていらっしゃった中で、お二方と協力することによって、これまでできなかったところで何が生まれるのかというところを教えていただけますか。
小松副市長:
空き家・空き地対策は神戸市もこれまで様々な施策を取り組んできておりますけれども、今回こういった2者の方が事業をやっていただくということで、ある意味、リノベーションをやっていただくということで、そういったことと、例えば学校がある地域、それから、今後計画していただける学生寮を整備するような地域、そういった地域の方々との、新たな住民と元々いらっしゃった住民との交流とか、そういったところで、再度まちの魅力なり、その地域の利便性を再認識していただいて、定住なり、新たな交流の促進に十分つながっていくと考えていますので、そういったことでまちの活性化を図っていきたいと、それぞれのエリアの活性化を図っていきたいと考えています。
今までと違うのは、やはりこういうのは、先ほども申し上げましたが、空き家所有者とか、そういう権利者、関係者と行政が調整することはたくさんあったんですけれども、ここにこういった民間事業者が参入していただくことによって、そういったところのマッチングによって新たな可能性が生まれてくると思いますので、そういったところを期待して、この事業を今後も積極的に進めていきたいと考えています。
記者:
学生寮の整備運営も1つ、このプロジェクトの中で生まれていくゴールというか、イメージの1つと思っていいんでしょうか。
小松副市長:
学校のほうはRePlayceさんでやっていただきますし、学生寮とか、そういった住居関係はCHINTAIさんのほうでやっていただく分担になってございますけれども、先ほども申し上げましたが、先ほど、空き家が多くて、坂のまちエリアで1番から5番で場所を示しておりましたが、こういったエリアにやはり空き家・空き地が多いので、そういったところをCHINTAI様の御支援をいただきながら、例えば学生寮へのリノベーションとかやっていただければ、やはり新たな人口というか、定着が生まれますので、そういったところに期待しながら取り組んでいきたいと考えています。
記者:
お二方も、もしよければ、ゴールのイメージで考えていらっしゃることあればお願いします。
山本代表取締役CEO:
まず前提としまして、弊社が取り組んでいくべき課題みたいなところでいきますと、そもそも今、全国的に不登校は増えておりまして、通信に通う人は増えています。それは、ネガティブにひきこもりをしていますとかではなくて、今、既存の学校にははまらない子たちがどんどん増えていて、今、全国で10人に1人が通信制に通うという時代になっております。それは自ら既存の学校教育とは違う教育を選択するという学生がどんどん増えているというのが今の現状になっています。
我々、キャリア教育とかをやっていく中での大事なポイントとして、これは京都大学のデータとかでも出ていますけども、高校2年生がターニングポイントと言われるんですね。キャリア観を醸成したりですとか、いわゆる非認知能力、課題解決力も含めてですけども、意識しながら学んでいって、それからの人生に影響する選択肢があるのは実は高校2年生というタイミングでして、我々はこの高校という場で、地域での活動だったりですとか、その中で例えば地元の企業様と、今、我々、基本的には全国規模の大企業さんとやらせていただいているケースが多いですけども、これから地元の企業様ともどんどん連携はしていきたいなというふうに思っていまして、地元の企業様と連携しながら地域の課題解決をしていって、例えばまちづくりだったりですとか、そこで起業していくとか、そういったことに興味を持つ生徒が1人でも2人でも増えていけば、その地域は活性化していくんじゃなかろうかなというふうに思っておりまして、我々としては、もちろん高校3年間の話だけではなくて、その後、学生たちがその地域で活躍していくというところをサポートしていきながらつくっていけたらなというふうに思っております。
奥田代表取締役社長:
CHINTAIのところは、「社会貢献プロジェクト」のページを映してもらいたいんですけども。ありがとうございます。CHINTAIは「社会貢献プロジェクト」なるものをやっていまして、こちらは地域住民ですとか自治体、こちらのほうと連携をして、地域の魅力の向上ですとか課題解決に取り組む、そういったことで、まちの価値ですとか物件の価値、こういったものを向上させるというものを目指したプロジェクトです。実際に不動産オーナーの方ですとか不動産関係・関連企業の方々、5,000名を超える方々に今、御賛同いただいておりまして、そういった方々の御賛同を基に、日本全国、いろいろな行政もしくは動物園、水族館、図書館、児童館、こういったところと連携をして、まちの価値、物件の価値向上につながるようなものを進めている。なので、本取組、本連携が、神戸の、今、課題を抱えている空き家が広がっているような地域・エリアのまちの向上、価値の向上、魅力の向上につながるものというふうに考えております。
また先ほどお話しした副教材のところに少し触れるんですけど、現在、1,050校の高校で導入をいただいていて、生徒数でいうと17万人を超える高校の生徒の方に対して授業を実際に今、実施をしておるという状況でございますので、ここは、兵庫県、全部で211校ほどあるかなと思っているんですが、こちらの導入数を神戸市様と連携して100%に近づけていきたいと。これをする目的としましては、先ほども申し上げたんですけど、やはり、2022年に成年年齢が18歳に引き下がりましたと。では、18歳、高校3年生の4月1日に誕生日を迎える方は、いろいろな契約を保護者の方の同意なく結べてしまうと。そうすると、やはりトラブルに巻き込まれるケースがあると。この導入率を高めることによって、兵庫・神戸に住まう高校生の方々がトラブルに遭う、そういった件数を減らす、ゼロにできたら理想的だと思いますし、その高校で学んだ方々が、じゃ、実際一人暮らしをする際に、正しい知識を持って部屋探しをしていただけると、それはオーナーさんからも正しく利用いただけるということにつながると思うので、こういった面から社会課題の解決につなげていきたいなというふうに思っておりますし、実現できるかなというふうに確信しております。
記者:
副市長に最後に。フィールドは鵯越になるんですか。それとも限らずなんでしょうか。
小松副市長:
鵯越に限ったわけじゃなくて、山麓部の空き家が多い地域がございますので、そういったところの活性化という視点で、たまたま、今、鵯越駅で可能ではないかというのがございますので、まずそこをCHINTAI様に御検討いただきながら、我々もマッチングという形で協力させていただいて、うまく事業ができればということで考えています。ですから、必ずしも鵯越じゃなくて、ほかの地域でもこういう条件が合うところがあれば、我々は積極的にまちの活性化という意味で取り組んでいきたいと考えています。
記者:
今回、副市長にお伺いさせていただきたいことが、神戸の住民や地域団体と学校が連携して活動する際に、市として特に大切にしたいポイントを教えていただきたいです。
小松副市長:
今までお住まいの、住んでおられる、いわゆる旧住民の方と新たに外から入ってこられる新住民の方、これはやっぱり両者がダイレクトにコミュニケーションというのはなかなか難しいでしょうから、やっぱりそこの間の接着剤を神戸市という行政で担ってマッチングさせていただくと。そういったところから交流が生まれて、多世代コミュニティーみたいなものが醸成されて、よりよい持続可能なまち・エリアになっていくような、そういった取組を最大限支援していきたいと考えています。
記者:
ありがとうございます。この旧住民の方の声というのはやっぱり重視していきたいというふうに考えられていますか。
小松副市長:
当然そこにもともとお住まいの方がいらっしゃいますので、そういった方たちの声は踏まえて、この事業は、私が考えるに、お互いが相乗効果がある事業だと考えていますので、そういったところでは丁寧に説明をしながら御理解をいただいて進めていきたいと考えています。
記者:
すみません、ちょっと1つだけ。学生寮なんですけど、どれぐらいの規模とかというのは何か考えていらっしゃいますか。数十人とか何かそんな丸いイメージで結構なんですけど、規模感がもし分かれば。構想で結構なので。
山本代表取締役CEO:
ちょっとまだ生徒の数も決まっているわけではないので、例えば、スクールのほうの生徒が30人に対して30人分用意するって、多分30人がみんな学生寮に入るとは限らないので、そのあたり、今後展開していく中で決めていく話になるかなというふうには思っています。いきなり大きくはスタートできないと思っているので、まずはスモールでスタートさせていきつつ、そういう学住一体型でこういう教育ができますということの証明ができていけばいいのかなというふうに思っています。
記者:
HR高等学院さんの生徒の人数はどれぐらいになりそうなんでしょうか。
山本代表取締役CEO:
まずは1校舎当たりですけども、通学でいくとは80人程度が入る場所というところは考えております。でも、それは同時に80人入るというよりは、通信ですと結構自分のペースで通うケースが多いので、同時に三、四十人ぐらいが入るような、何かそういった場所というところをベースとして考えています。
―― 了 ――
動画再生ソフトウェアのダウンロード
このページは接続環境によって、映像・音声などがみだれたり、スムーズな視聴ができない場合があります。あらかじめご了承ください。