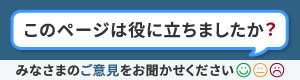ホーム > 区役所 > 北区(北神区役所) > 北区(北神地域)の紹介 > 有野町の紹介
有野町の紹介
ページID:37881
ここから本文です。
有野町は、南から大池、唐櫃、有野、二郎へと有野川流域に沿って開けた地域です。昭和3年の神有鉄道(現在の神戸電鉄)の開通により、急速に人の往来が増え、都市文化が浸透しました。その後、東大池、唐櫃台、有野台、藤原台、北神星和台などの大規模な住宅団地が開発されました。北区北部の中心地として、岡場には行政施設や商業施設などが集積しており、平成31年4月には北神区役所が開設され、隣接して北神図書館やこべっこあそびひろばが整備されています。
一方で、伝統ある仏閣や神社が各地に現存しており、摂津国有馬郡の一の宮であった「有間神社」をはじめ、二郎の「大歳神社」、平清盛ゆかりの「多聞寺」などが有名です。また農業では、大正時代から生産が始まったと言われる二郎地区のイチゴ栽培が有名で、1月~6月頃までイチゴ狩りと沿道直売が行われています。
有野町の名所・旧跡
有間神社
最寄りのバス停:神姫バス 有間神社停留所
昔から有馬郡の一の宮として有馬総社といわれていた。もともと、山口町下山口(現在の西宮市)に鎮座していたものを霊亀年間(715年~716年)の六甲山の洪水により、現在の地に移築したといわれている。境内には、「有馬社」と刻まれた社号碑が2基ある。クスノキの下にある1基は建立当時のものである。また、御旅所には子安石があり、昔から安産の神として信仰されている。
専念寺
最寄り駅:神戸電鉄 有馬口駅
天正2年(1574)以前に創建されたと推定される。建武のころ赤松則村がこの地に滞在していたといわれており、境内に則村と息子則祐の供養碑がある。また、境内には藤原初期の地蔵尊があり、おしゃもじ地蔵という名で親しまれている。また、寺の周辺にはあじさいが約500本植えられており、「あじさい寺」とも呼ばれている。
多聞寺
最寄り駅:神戸電鉄 神鉄六甲駅
多聞寺周辺地図(外部リンク)孝徳天皇のころ(645年~654年)、現在の地より南東の古寺山に創建されたといわれている。境内には樹齢300年以上のかやの大木があり神戸市より「名木」の指定を受けている。
西光寺
最寄り駅:神戸電鉄 神鉄六甲駅
西光寺周辺地図(外部リンク)1873年(明治6年)の火災により、寺院の記録などが全て焼失。また、1919年(大正8年)に観音堂、地蔵堂も焼失している。境内に「石風呂」とよばれる一畳ほどの御影石があり、石棺であるとか、神嘗祭(にいなめさい)用の米作りの従事者がこれに入って身を清めたという説が伝えられている。