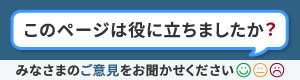玉津南公民館周辺の「野鳥観察日記」
最終更新日:2026年2月12日
ページID:46788
ここから本文です。
玉津南公民館の周辺には自然がいっぱい!そこには多くの野鳥の営みも。このコーナーでは、近くで会える野鳥たちを紹介します。
- アオサギ
- イソヒヨドリ
- エゾビタキ
- オオバン
- カワセミ1
- カワセミ2
- キンクロハジロ
- ケリ(R6)
- ケリ【ひな】
- ゴイサギ
- コガモ
- コゲラ
- コサギ
- コチドリ
- ジョウビタキ
- スズメ
- ハシビロガモ
- ヒクイナ
- ヒバリ
- ミコアイサ
- ミサゴ
- メジロ
- モズ
- ルリビタキ
ジョウビタキ
 オス
オス  メス
メス
厳しい寒さの中でも梅が咲いてきました。公民館近くや明石公園の梅や桜の木に飛んできて、「ヒー ヒー ヒー」「カッ カッ カッ」と鳴いて縄張りを主張しているのがジョウビタキです。左がオス。右がメスです。
オスは頭が灰色で背中が黒に白の斑点、お腹がオレンジと鮮やかな配色をしています。
メスは地味な茶色基調ですが一部にオレンジが入り、白の斑点は一緒です。
秋に北方から渡ってきて、4月頃には帰っていきます。低い枝にとまって、地表の虫を捕食し、同じ枝に戻る習性があります。目がまるまるで愛くるしい鳥です。
2026年2月9日
キンクロハジロ

カモ類「キンクロハジロ」。写真は、明石公園剛ノ池のキンクロハジロのオス2羽です。(後方はホシハジロ)オスは黒い身体に白く見える羽根に黄色い目がチャーミング。頭の後ろに冠羽が特徴です。冬鳥として明石公園に飛来していますが、飛来地は池の他、海や湖などさまざまです。水中に潜って魚や貝を捕食します。夜に移動することも多く、「鳥目」というのは当てはまらないようです。
2026年1月14日
ミサゴ

今回紹介するのは、猛禽類の「ミサゴ」です。写真は、明石公園桜堀の上空を飛んでいるミサゴです。明石公園にはこのほか「トビ」「オオタカ」「ハヤブサ」などの猛禽類が棲息しています。ミサゴは水面の上空から狙いを定め急降下し、鯉やボラなど大きな魚を「わしづかみ」にして捕食します。下から見ると翼が白っぽくてスマートな、かっこいい鳥です。
2025年12月17日
イソヒヨドリ

よく通るきれいな声で鳴く青い鳥はな~に?」という質問がよくあります。
もともとは沖縄など南方の鳥、イソヒヨドリです。名前はヒヨドリですが、ツグミの仲間です。最近は温暖化の影響で本州の都会のビルでもよく見られ、ムカデなどの虫を好んで食べます。公民館近くでもきれいな声で鳴いています。
2025年6月21日
ケリ

初夏になり子育ての季節になりました。明石公園の剛ノ池では今年もカワウとアオサギの子育てが始まっています。
玉津の鳥、ケリも子育てに大忙しです。水を張る前の田んぼでヒナが数羽走り回り、親鳥のつがいはそばで天敵からの危機に備え目を光らせています。厳しい生存競争の中、今年は何羽育つのでしょう。あたたかく見守りましょう。
2025年5月1日
ゴイサギ

明石公園で見る機会の少ない鳥がいました。「ゴイサギ」です。北海道から九州にかけて見られるサギ科の鳥ですが、アオサギよりも濃淡がはっきりしていて小柄です。目が赤く足が黄色いのが特徴です。「桜堀」でじっと魚の動きを追っていました。
2025年2月17日
ヒクイナ

冬の明石公園には珍しい鳥の姿も見られます。
「桜堀」の湿地に「ヒクイナ」が来ています。全体に地味な灰色で顔は赤色、尾の裏側はきれいな模様になっています。夏は山地の田や湿地で暮らし、冬は南へと渡りますが、一部は本州に残ります。絶滅危惧種に指定されている地域もあるようです。
2025年1月21日
カワセミ

「トライやるウィーク」で玉津中学の生徒が公民館にやってきました。
館周辺の自然学習のために一緒に野鳥観察をしました。この日観察できた野鳥は、イソシギ、シジュウカラ、ハクセキレイ、アオサギ、ヒドリガモ、オオバン、ハシビロガモ、ホシハジロ、オカヨシガモ、カワウなど。伊川を渡って公民館に戻ろうとしたときでした。「いた!」と一声が。カワセミでした。前日も2羽で縄張り争いをしている現場を見ましたが、この日は1羽。美しいコバルトブルーの鳥を見て生徒たちは「かわいい」と大喜びでした。
2024年11月13日
オオバン

ようやく秋がやってきました。
水鳥も公民館近くの伊川・明石川や明石公園の池を目指して飛んできていて、日に日に種類が増えています。
今回紹介するのは明石公園・剛ノ池のオオバンです。黒の地味な鳥ですが、嘴から額までが白いのが特徴です。水草・虫・小魚を食べます。目が赤いので黒白赤のコントラストがきれいな鳥です。
2024年11月12日
エゾビタキ

まだ暑い日が続いていますが、「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通り、田んぼではヒガンバナが咲き、野鳥にも秋を感じさせる姿が見え始めました。
写真は9月26日に明石公園で撮った「エゾビタキ」です。「エゾ」と言っても北海道より北のシベリアやカムチャッカで夏を過ごし、子育てが終わって冬になる前に南へ向かいます。目標は遠くフィリピンやニューギニアという長距離の渡り鳥で、絶滅危惧種にも登録されています。そんな鳥が公民館の近くを訪れているなんてすごいですね。
2024年9月26日
ケリ
玉津の夏の鳥といえば、やはりケリです。4~5月にふ化したヒナの半数足らずは受難をくぐり抜けて生き残り、6月末には羽ばたちますが、夏の間は家族や集団で生活します。玉津の田畑はケリ家族の生活の場です。幼鳥も足で土を震わせて、飛び出してくるミミズや虫を食べて、夏の間に大人と同じくらいに成長します。

「ケリの親子(手前がヒナ)」2024年4月21日撮影

「育った幼鳥」2024年6月26日撮影
玉津南公民館の北東部の田んぼにいます。
ようやく幼鳥が親鳥と同じくらいの大きさになり子育てが一段落した時期です。
ケリは日本最大のチドリの仲間です。
気が強く、縄張り意識が高いため、他の鳥や動物が近づくと「ケケケケケ」と甲高い声を発して威嚇し上空を飛び回ります。
そのため迷惑がられる場合もありますが、羽を広げると「茶」「白」「黒」のパターンが美しい鳥です。
「ケケケケケ」と甲高い声が聞こえたらこの鳥かな?と思い出してください。
コチドリ

夏になって鳥の種類もかなり減りましたが、夏にしか会えない鳥もいます。写真は公民館近くの田んぼでのコチドリです。スズメくらいの小さな鳥で、目の周り(アイリング)の鮮やかな黄色がチャーミングです。夏になると伊川や明石川の小石の多い河原で産卵し、子育てします。ヒナは小石の色に溶け込んで、双眼鏡でもみつけるのは困難です。しかし人や天敵が近づくと、気を引くために親鳥が鳴いたり、負傷したふりをするため、その周辺にいるということがわかります。
2024年6月13日
スズメ

写真は公民館近くでのスズメの親子です。くちばしの根元が黄色い左の方が子どもです。5~6月といえば、野鳥にとって子育ての季節です。公民館の庇の下にもツバメが巣を作って卵を抱いていましたが、カラスに狙われて巣ごと落下してしまいました。卵からふ化しても多くのヒナは自然の中で命を落とします。このスズメの子どもが元気に育つことを願わずにいられません。
2024年5月28日
コゲラ

写真は桜満開の明石公園剛ノ池近くのコゲラです。スズメくらいの大きさで、最小のキツツキです。白黒の地味ですが美しい模様の鳥で、木の中の虫や実などを食べます。普段はシジュウカラなどのカラ類と一緒に行動することが多いようです。近くの木の上から「ココココココ」と木を突っつく音がしたらコゲラです。「ズイーッ」という声で鳴きますので、注意深く観察しましょう。
2024年4月19日
ヒバリ

写真は公民館の北へ5分の田んぼのヒバリです。3~4月の春になると「ピーチクパーチク♪ヒバリの子♪」の歌のとおり、小さな身体に似合わず大きないい声で鳴いています。まっすぐ上空に上がって「ピーチクパーチクチチブチョイチリリ」と鳴いて、自分のテリトリーを主張します。鳴き終わるとスーッとまっすぐに降りてきます。
2024年3月23日
メジロ

暖冬は、野鳥にとって冬はエサの少ない試練の日々。そんな冬を耐え抜いて、ようやく春を迎えました。写真は明石公園剛ノ池近くの梅林でのメジロです。抹茶色の身体に眼の周りが白の小鳥で、色からよくウグイスと間違われます。小さなくちばしの中にある先がスポンジ状になった舌で花の蜜を吸います。みかんなどの果実も好物です。さあ!メジロに会いに梅林に出かけましょう!
2024年2月20日
モズ

写真は、公民館近くの電線に止まった「モズ」のオスです。最小の猛禽類で「キイキイ」「ギュンギュン」という鳴き声がモズの「高鳴き」と言われます。カエルや虫を捕まえて尖った枝などに突きさす「早贄(はやにえ)」とうい行動で有名です。その目的は、エサが減る冬季に食べるためと言われていましたが、繁殖の際、メスの人気を得る行動でもあることが分かってきました。
2024年2月20日
ルリビタキ

真冬の到来とともに、野鳥も増えてきました。写真は、明石公園のルリビタキ(雄)です。雄は全体の青とお腹のオレンジのコントラストが美しいです。夏の間は北海道や亜高山で過ごし、冬になると明石公園にも現れます。お気に入りの枝から飛んでエサを取って、その後同じ枝に戻るという、他のヒタキ類と同じ習性を持っています。
2024年2月20日
ミコアイサ

12月に入り、明石公園周辺にも冬鳥が増えてきました。9日の親子野鳥観察会の日には、ユリカモメが飛来しました。12日には昨年数羽しか見られなかった「ミコアイサ」が、剛ノ池で倍以上観察されました。下の写真の白い方がオスです。「巫女」の衣装のように真っ白で目の周りが黒。パンダのような愛嬌のある模様です。潜って魚を捕まえるのが上手で、潜る瞬間、尾羽がカモノハシの尾のようにしゃもじ型になります。
2023年12月7日
カワセミ

12月の親子野鳥観察会では「カワセミ」を最後に見ることができました。お腹がオレンジで背中がコバルトブルーの「清流の宝石」と呼ばれる美しい鳥です。「チー」と甲高い金属音のような声が聞こえたら近くにいます。枝から水面の小魚を狙って飛び込んで捕え、頭から上手に丸呑みします。公民館近くの明石城の堀や伊川、明石川に棲息しています。ぜひ美しいブルーを目に焼き付けてください。
2023年12月2日
コガモ

写真は公民館近くの伊川にいるコガモのオスとメスです。日本に渡来する鴨の中では最も小さな鴨です。11月に来た時はオスの模様はメスと同じでしたが、冬の間に美しい青と赤茶の模様に変わりました。お尻の白の斑点も美しい鳥です。もうすぐ北へと帰って行きます。
2022年9月9日
ハシビロガモ

北風に乗って北の国から南下する冬鳥。公民館近くの明石公園や伊川にも多くのカモ類がやってきています。今回紹介するのは「ハシビロガモ」。名のとおり嘴の先が広く、雄は後頭部の青と胸の白、胴の茶のコントラストが美しい鳥です。剛ノ池の中央部で10羽くらいが輪になってグルグル回っています。群れで回ることで効率よくプランクトンを集めて食べます。そのチームプレイをぜひ観察してください。
2022年2月2日
アオサギ

写真は明石公園の「アオサギ」です。「アオサギ」と言いますが、青ではなく、灰色です。剛ノ池の南西部では「カワウ」と「アオサギ」がコロニーを作っています。大人になると90センチを超える大きさになりますが、池の周りにはまだ小さな子供のアオサギも多くいます。よくありませんが、餌を与える人がいるようで、ここのアオサギは人慣れしていて近寄っても逃げません。
普通は「ギャー!」と汚い鳴き声を残して飛んでいきます。
2021年10月28日
コサギ

写真は公民館南側の伊川のコサギです。よく「シラサギ」と言いますが、白いサギにも3種類あります。「コサギ」「チュウサギ」「ダイサギ」です。名の通り大きさで分別します。コサギは一番小さく60センチくらいです。他の白いサギとの見分け方は「足」が黄色いところです。川の中を辛抱強く見て、瞬時に魚を取ります。
2021年10月11日