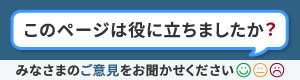ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 介護サービス事業 > 神戸市の規定・様式類 > 負担限度額認定証の申請
負担限度額認定証の申請
最終更新日:2025年9月9日
ページID:10742
ここから本文です。
目次
- 制度の概要
- 制度の対象者(要件)
- 食費・居住費の利用者負担額(日額)
- 申請の手続き
- 認定結果の通知(認定証の交付)
- 課税層の方への特例減額措置
- 特定入所者介護(予防)サービス費の差額支給
- 提出先・お問い合わせ先
- 更新申請書の発送に関するよくある質問
制度の概要
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所中(ショートステイ含む)の方の食費・居住費は、原則、ご本人の自己負担です。
ただし、下記の要件に該当する場合は、申請により「介護保険 負担限度額認定証」の交付を受け、食費・居住費の負担軽減を受けることができます。
負担軽減の有効期間は、毎年8月1日~7月31日です。継続して認定を受けるには、毎年申請が必要です。
デイサービスや有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・ケアハウス・グループホーム・(看護)小規模多機能型居宅介護などの食費・居住費は、軽減の対象外です。
※給付制限(給付額減額)を受けている場合、申請により「介護保険 負担限度額認定証」を交付することはできますが、制限を受けている期間中は軽減が受けられません。
制度の対象者(要件)
下記の1に該当する方、または、下記の2~4のすべてに該当する方が対象です。
- 生活保護を受給していること
- 世帯全員(本人を含む)が、市民税非課税であること
- 配偶者が、市民税非課税であること
- 本人および配偶者の現金・預貯金・有価証券・債権等の資産が、下表の金額以下であること
| 対象者 | 資産額 |
|---|---|
| 本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、80.9万円以下の方 | 650万円以下 |
| 本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、80.9万円超120万円以下の方 | 550万円以下 |
|
本人の年金収入額と、その他の合計所得金額の合計額が、120万円超の方 |
500万円以下 |
| 本人の年齢が40歳~64歳の方 | 1,000万円以下 |
配偶者がいる場合は、上記の資産額に対し、一律に1,000万円を加算した金額になります。
※年金収入額には、課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含みます。
※勘案の対象となる預貯金等の種類は「申請の手続き」内【申請に必要な書類】の「添付書類・資産要件等のご案内」をご確認いただき、ご不明な点はお問い合わせください。
食費・居住費の利用者負担額(日額)
負担限度額認定を受けた場合の負担額
利用者負担段階区分:第1段階
- 対象者
- 生活保護を受給されている方
- 老齢福祉年金を受給されている方
- 食費:300円
| 部屋の種類 | 居住費(滞在費) |
|---|---|
| ユニット型個室 | 880円 |
| ユニット型個室的多床室 | 550円 |
| 従来型個室(特養) | 380円 |
| 従来型個室(老健等) | 550円 |
| 多床室(相部屋) | 0円 |
利用者負担段階区分:第2段階
- 対象者
- 本人の年金収入額と、その他の合計所得金額※の合計額が、80.9万円以下の方
| 食費 | 部屋の種類 | 居住費(滞在費) |
|---|---|---|
| 施設入所 390円 |
ユニット型個室 | 880円 |
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | |
| ショートステイ 600円 |
従来型個室(特養) | 480円 |
| 従来型個室(老健等) | 550円 | |
| 多床室(相部屋) | 430円 |
利用者負担段階区分:第3段階①
- 対象者
- 本人の年金収入額と、その他の合計所得金額※の合計額が、80.9万円超120万円以下の方
| 食費 | 部屋の種類 | 居住費(滞在費) |
|---|---|---|
| 施設入所 650円 |
ユニット型個室 | 1,370円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | |
| ショートステイ 1,000円 |
従来型個室(特養) | 880円 |
| 従来型個室(老健等) | 1,370円 | |
| 多床室(相部屋) | 430円 |
利用者負担段階区分:第3段階②
- 対象者
- 本人の年金収入額と、その他の合計所得金額※の合計額が、120万円超の方
| 食費 | 部屋の種類 | 居住費(滞在費) |
|---|---|---|
| 施設入所 1,360円 |
ユニット型個室 | 1,370円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,370円 | |
| ショートステイ 1,300円 |
従来型個室(特養) | 880円 |
| 従来型個室(老健等) | 1,370円 | |
| 多床室(相部屋) | 430円 |
利用者負担段階区分:第4段階
- 対象者
上記の第1~第3段階以外の方
- 食費および居住費
施設との契約額を支払うことになります。
※「その他の合計所得金額」とは、収入金額から必要経費などを控除した所得金額の合計額から、公的年金等に係る雑所得と、土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除額を除いた金額のことです。(基礎控除・配偶者控除などの所得控除前の金額です)
- 従来型個室のうち、「老健等」とは、介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型施設のことです。
- 施設に入所した場合の利用者負担は、食費・居住費のほかに、介護保険サービス費の負担があります。また、施設によっては、日常生活費・特別な室料等がかかる場合があります。
- 特別養護老人ホームの旧措置入所者(2000年(平成12年)3月31日以前から特別養護老人ホームに入所されている方)で負担軽減を受けている方のうち、2005年(平成17年)9月末において介護サービス費の負担割合が5%以下の方には、従来の負担額を上回らないような措置が取られます。
負担限度額認定を受けていない場合の負担額
下表の金額は、国が定める食費・居住費の標準的な額(国の基準費用額)です。
※実際に施設へお支払いいただく金額は、利用者と施設との契約により定められますので、利用される施設により異なります。
| 食費 | 部屋の種類 | 居住費(滞在費) |
|---|---|---|
| 1,445円 | ユニット型個室 | 2,066円 |
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | |
| 従来型個室(特養等) | 1,231円 | |
| 従来型個室(老健・医療院等) | 1,728円 | |
| 多床室(相部屋)(特養等) | 915円 | |
| 多床室(相部屋)(老健・医療院等)(注) | 697円 | |
| 多床室(相部屋)(老健・医療院等) | 437円 |
(注)「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設(※)又は「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る。)が対象。
※算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(ただし、令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)におい
て、「その他型」又は「療養型」として算定した月が7か月以上であること。
申請の手続き
認定証の有効期間
「介護保険 負担限度額認定証」の有効期間は、【申請月の1日から、次の7月31日まで】です。
介護保険施設への入所・ショートステイのご利用予定がある際には、利用する前月まで(遅くとも当月中)に申請してください。
昨年度に負担限度額の認定を受けており、かつ「介護保険 負担限度額認定証」を利用された方には、毎年6月下旬頃に更新のご案内をお送りしています。
申請に必要な書類
申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
- 神戸市介護保険負担限度額認定申請書(PDF:436KB)
- 預貯金等の資産を証する資料
ご提出いただいた内容を確認し、区役所からご連絡する可能性があります。
※申請の際には、下記の案内・記入例もご確認ください。
ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
※区役所・北須磨支所に来庁して申請に関する相談をされる場合は、下記の書類も必要です。
- 被保険者の、「介護保険 被保険者証」または「顔写真付きの本人確認書類(1点)」
本人確認書類とは
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・運転経歴証明書・その他官公署の発行する顔写真付きの証明書のことを指します。
申請に必要な書類(認定証を紛失・破損した場合)
申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
- 介護保険 被保険者証等 (再)交付申請書(PDF:82KB)
- お手元にある「介護保険 負担限度額認定証」(汚損・破損等で再交付する場合のみ)
ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
※区役所・北須磨支所に来庁して申請される場合は、下記の書類も必要です。
- 被保険者の、顔写真付きの本人確認書類(1点)
- 代理人の、顔写真付きの本人確認書類(1点)(代理人が申請される場合のみ)
- 再交付申請・認定証等の受領にかかる委任状(代理人申請かつ、被保険者の本人確認書類がない場合)
本人確認書類とは
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・在留カード・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・運転経歴証明書・その他官公署の発行する顔写真付きの証明書のことを指します。
※委任状の様式はありませんが、委任内容および、委任者および受任者の住所・氏名を記入の上、それぞれの印鑑を押印してください。
提出先・提出方法
下記「提出先・お問い合わせ先」の窓口または、郵送にて申請
電子申請のご案内
マイナポータルぴったりサービスより、電子申請ができます。
認定結果の通知(認定証の交付)
- 負担限度額認定の申請をされ「承認」の場合は、後日郵送で「介護保険負担限度額認定証」をお送りします。(「不承認」の場合は、不承認通知をお送りします。)
- 8月1日から有効の「介護保険 負担限度額認定証」は、6月~7月に申請いただいた場合でも、8月上旬~中旬頃以降にお送りしています。
- 介護保険施設への入所・ショートステイを利用される際は、「承認」「不承認」に関わらず、必ず施設にご提示ください。
- 「承認」となった場合でも、行政機関や金融機関への調査の結果、遡って利用者負担段階区分の変更または「不承認(取消)」となることがあります。なお、その場合は、再度「介護保険 負担限度額認定証」をお送りした上で、既にご利用済みの期間の返還請求(給付費返還金)をさせていただきます。
課税層の方への特例減額措置
市民税課税の世帯の場合は、「介護保険 負担限度額認定証」の交付は受けられず、介護保険施設における食費・居住費は、施設との契約によります。
ただし、下記の要件に該当する場合は、申請により、特例として食費・居住費の負担軽減を受けることができます。(※ショートステイは対象外です)
制度の対象者(要件)
下記の1~7のすべてに該当する方が対象です。
- 2人以上の世帯であること(※1)
- 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階(施設との契約金額)の食事・居住費を負担すること
- 世帯の年間収入(※2)から、施設の利用者負担(※3)の年間見込額を引いた額が、80.9万円以下となること(※4)
- 世帯の現金・預貯金・有価証券、債権等の金額が、450万円以下であること
- 世帯および配偶者が自ら住んでいる家屋等、日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を所有していないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
- 軽減を受けようとする期間が、給付制限(給付額減額)を受けている期間ではないこと
※1 介護保険施設の入所にあたって世帯分離した場合は、世帯分離前の世帯で計算します。なお、別世帯に配偶者がいる場合は、上記の世帯に加えます。
※2 年間収入とは、公的年金等の収入金額と、合計所得金額(公的年金等に係る雑所得は除く)を合計した額から、土地等又は建物等の譲渡に係る長期譲渡所得 又は短期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額です。遺族年金や障害年金などの非課税所得は含みません。
※3 利用者負担とは、「介護保険 負担割合証」に記載された負担割合に基づく自己負担額と、食費・居住費を合計した金額です。(高額介護サービス費の支給がある場合は、利用者負担合計額から差し引きます)
※4 本人と配偶者・世帯員が同時に介護保険施設に入所している場合も対象になります。
その際は、世帯の年間収入から、入所者全員の利用者負担の年間見込額を差し引きます。
なお、配偶者・世帯員が介護保険施設以外に入所している場合や、ショートステイ等を利用している場合は、配偶者・世帯員の利用者負担は差し引けません。
申請に必要な書類
申請書は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
「神戸市介護保険 収入等申告書」の「課税層の特例減額措置申告に必要な利用料に関する施設の証明欄」は、入所される施設に記入・押印を依頼してください。
※申請の際には、下記の案内もご確認ください。
ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
特定入所者介護(予防)サービス費の差額支給
介護保険施設の入所者または、ショートステイ利用者の方で、サービス事業所に「介護保険 負担限度額認定証」を提示できずに事業者が定める通常料金を支払った場合、国の定める基準費用額と、負担限度額認定が適用された金額との差額を、申請により支給します。
制度の対象者(要件)
下記の1~5のすべてに該当する方が対象です。
- 負担限度額認定の対象となる、介護保険サービスを利用していること
- 介護給付の対象であること(外泊などの、介護給付費対象外のものは支給できません)
- 利用当時の状況が、負担限度額認定の要件に該当していること
- 受給権消滅時効が到来していないこと
- 事業者に支払った食費・居住費の両方が、国の定める基準費用額以下であること
対象になるかどうかが不明な場合は、下記「提出先・お問い合わせ先」までお問い合わせください。
申請に必要な書類
申請書等は、下記からPDFデータをダウンロードできます。
A4サイズで印刷の上、ご使用ください。
- 特定入所者介護(予防)サービス費支給申請書(PDF:390KB)
- 事業者に支払った食費・居住費の金額がわかる「領収書」(原本)
- 食事の提供に要する費用の明細票(PDF:96KB) ※「領収書」に明細がある場合は不要
- 居住等に要する費用の明細票(PDF:95KB) ※「領収書」に明細がある場合は不要
- 振込口座のわかるもの(通帳等) ※利用当時に有効な「負担限度額認定証」が交付されている場合は不要
ダウンロードできない場合は、下記の「提出先・お問い合わせ先」にご連絡いただきましたら、郵送でお送りします。
申請するサービス利用月に負担限度額認定を受けていない場合は、併せて負担限度額認定の申請が必要です。
提出先・お問い合わせ先
お住まいの区の区役所・支所の介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先
更新申請書の発送に関するよくある質問
Q1 申請書が届いたがこれは何ですか。毎年申請が必要ですか。
A1 今回送付している書類は、8月1日以降有効な「負担限度額認定証」を交付するために必要な申請書です。
昨年度「負担限度額認定証」の認定を受けておられ、かつ、「負担限度額認定証」をご利用されている方にお送りしています。
介護保険施設(特養・老健・療養病床・介護医療院)への入所または、ショートステイ利用時にかかる食費や居住費(滞在費)の負担は原則として自己負担ですが、一定の要件を満たす方には「負担限度額認定証」を交付し、負担を軽減しています。
「負担限度額認定証」には有効期限があり、毎年7月31日までとなります。
8月1日以降から有効な「負担限度額認定証」の交付を受けるには、毎年申請が必要です。
Q2 いつまでに申請すれば良いですか。
A2 今回送付している申請書の提出期限は、令和7年7月22日(火曜)必着です。
同封している返信用封筒をご利用の上、お住まいの区の区役所・支所へ送付してください。
提出期限を過ぎても申請できますが、結果の送付が遅くなる場合があります。
Q3 本人以外が申請書を記入(代筆)しても良いですか。
A3 問題ありません。
なお、その場合は⑥申請者に関する状況欄には、申請書を記入された方の情報を記入してください。
Q4 申請書の書き方について
Q4-1 個人番号欄は書く必要がありますか。
A4-1 個人番号(マイナンバー)の記入は不要です。
記入例の太枠内(①現在の状況以下)の項目のみ記入してください。
Q4-2 「①現在の状況」の書き方を教えてください。
A4-2 現在、介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所している方(または入所予定日が決まっている入所予定の方)は、「1.」に〇を付け、下欄に入所(または入所予定)している施設の情報等を記入してください。
なお、施設の種類・施設の所在地・名称・入所日などが分からない場合は、施設にお問い合わせください。
それ以外の方は、「2.」に〇を付けてください。下欄の施設情報等の記入は不要です。
Q4-3 「④預貯金等に関する申告」に書く内容を教えてください。
A4-3 本人および配偶者の預貯金・有価証券(評価概算額)・その他(現金・負債等)の、各個人それぞれの合計金額を記入してください。
・預貯金欄は、お持ちの預金口座すべての残高を合計した金額をご記入ください。
・有価証券欄は、株式・国債・地方債・社債等がある場合、その評価額の合計金額をご記入ください。
・その他欄は、住宅ローン等の負債・預金口座以外の手許金(タンス預金等)の金額と内訳をご記入ください。
なお、該当がない場合は、それぞれの欄に0円とご記入ください。
また、住宅ローン等の負債額を記入される際には、金額の前にマイナスを記入してください。
同封されているチラシに、対象となる預貯金等の種類を記載しておりますので、提出の際にはご確認ください。
Q4-4 「⑦同意書欄」に書く内容を教えてください。
A4-4 本人および配偶者の住所・氏名をご記入ください。
なお、成年後見人・保佐人・補助人が記入する場合は、住所欄に本人の住所、氏名欄に「〇〇〇〇(被保険者名)の成年後見人(または保佐人・補助人)△△△△(成年後見人名)」と記入してください。
その上で、申請日から3ヶ月以内に発行された「登記事項証明書」等の代理権を証する書類を添付してください。
ご家族等が代筆される場合でも、被保険者本人および配偶者の住所・氏名をご記入ください。
ご家族等の住所・氏名の記入は不要です。
Q5 「⑦同意書欄」に押印は必要ですか。
A5 押印は不要です。(訂正印も不要です。)
Q6 添付書類は何ですか。
A6 本人および配偶者の、全ての預貯金等(定期預金・有価証券・投信含む)の口座残高・金融機関名・支店名・口座名義が分かる資料が必要です。(通帳のコピー等)
同封されているチラシに、対象となる預貯金等の種類や、添付資料として付けていただきたいものを記載しておりますので、提出の際にはご確認ください。
生活保護受給者の方、境界層該当者の方は各区介護医療係までお問い合わせください。
Q7 通帳はいつ時点で記帳したら良いですか。
A7 いずれの口座も、申請される月の1日以降に記帳してください。
なお、年金受取口座の場合は、最新の年金振込日以降に記帳してください。
申請される月の1日以降に記帳しても、最新の出入金の日付が申請される月の1日よりも前だった場合は、記帳日をコピーの余白部分に記載してください。
Q8 提出した申請書の審査の進捗を教えてください。
A8 申請書の受付・審査事務は、申請書提出先で行っていますので、お住まいの区の区役所・支所にご相談ください。
Q9 認定証はいつ届きますか。
A9 8月12日から発送予定です。
Q10 7月中に「負担限度額認定証」を発行してもらえますか。
A10 「負担限度額認定証」の認定には本人が属する世帯が非課税であることが必要となり、認定される段階は本人の前年中の年金収入等に応じて決まります。
これらの判定(基準日)は、有効期間開始日である8月1日付で行うこととなっています。
そのため、基準日前である7月中に送付することはできません。
負担限度額認定が承認となる場合は、8月中に、ご利用されている介護保険施設等に「負担限度額認定証」をご提示いただけましたら、8月1日に遡って軽減を受けることができます。
Q11 「負担限度額認定証」はどのような色・形状か。
A11 A4三つ折りで、白地に緑色の枠・文字です。
よく見られているページ
- 介護サービス情報の公表
- 介護保険事業者の運営指導
- 介護保険事業所一覧
- 【介護保険サービス事業者】指定・届出関係の各種手続き
- 介護サービス事業等の運営等の基準条例
- 事故発生時の報告(介護保険)
- 感染症・食中毒疑いの発生報告
- 償還払いの申請
- 介護給付費等過誤申立の手続
- 老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業者等の届出
- 別居親族による訪問介護サービス
- 障害者訪問介護利用者への支援措置
- 訪問介護の提供
- 負担限度額認定証の申請
- 福祉用具貸与の例外給付
- 福祉用具購入費の支給
- 有料老人ホーム
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減
- 地域密着型サービスの自己評価および外部評価
- 神戸市運営推進会議運営指針
- 神戸市小規模多機能型居宅介護費市町村独自加算
- 神戸市特別養護老人ホーム入所指針
- 神戸市軽費老人ホーム利用料等取扱要綱
- 市町村特別給付
- 特定事業所集中減算の判定の手続き(居宅介護支援)
- 介護保険住宅改修費の支給
- 高額介護(予防)サービス費等の支給
- がん患者の在宅介護の支援
- 主任介護支援専門員に対する履修証明書の発行
- 介護保険 第三者行為の届出
- 介護従事者の資格取得研修に対する受講費補助
- マイナポータルからの電子申請
- 神戸市軽費老人ホームの民間社会福祉施設職員給与改善費補助
- 介護保険証(被保険者証)等の再交付
- 介護保険の住所地特例制度
- 届出が必要なケアプラン