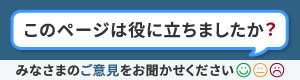定例会見 2025年2月17日
最終更新日:2025年2月17日
ページID:77956
ここから本文です。
- 令和7年度当初予算案について
令和7年度当初予算案について
司会:
それでは、これより2月の市長定例会見を始めさせていただきます。
市長、よろしくお願いいたします。
久元市長:
よろしくお願いいたします。私からは今日、神戸市の令和7年度当初予算案につきまして御説明申し上げます。
予算の内訳は、一般会計、特別会計、企業会計と分かれるわけですが、総額は2兆331億円、前年度比1,061億円、5.5%の増ということになっております。特に、一般会計につきましては1兆59億円ということで、前年度比1,002億円の増、11.1%の増ということになっております。この増加の主な原因は、新都市整備事業会計、これはかつて山、海へ行くという開発行政を担ってきた会計ですけれども、その使命が終了するということで、令和6年度末に閉鎖をいたします。これに伴う、新たに新設する会計への出資金の増、また、将来的な財政負担を軽減するための繰上償還による公債費の増などによるものです。同時に、後で御説明いたしますけれども、積極的に財政投資を行う、まちづくりのための事業、プロジェクトを積極的に展開するということで、投資的経費の増も一般会計の増加要因となっています。
予算規模ですけれども、今回2兆円を超えるということになりました。これは2005年以来、ちょうど20年ぶりということになります。震災の後、震災復旧復興事業のために、大幅に予算規模は増えましたけれども、その後、一段落をし、2005年には阪神・淡路大震災の復興基金への出捐金(にかかる市債償還)という特殊要因があったことなどから、この水準になったわけですけれども、その後、神戸市は、後で御説明しますけれども、行財政改革を進めるということで、予算規模を縮小させる、投資も抑える、経常経費も抑えるということで、減少傾向にありましたが、2015年ぐらいから予算規模は徐々に拡大をしてきました。今回、20年ぶりに2兆を超えるということになりました。
積極的に財政投資を行うということで、財源につきましては地方債を活用することになります。神戸市は震災後、大幅に市債を復旧復興事業のために活用いたしました。しかし、その償還がなかなか困難になるという見込みが立ったことから、そういう見通しのもとに積極的に行財政改革を進めるということと、投資を抑制するということで、それに伴って市債の発行も抑制をしてきました。2015年ぐらいから積極的に公共投資を行うということで徐々に増加をしてきまして、今回、市債残高は7,781億円程度になると。このうちには震災関連の市債残高がなお405億円残っておりますけれども、今後、積極的な財政投資によりまして市債残高は緩やかに増加をするということになると見込まれます。市債残高が増加をするということは、財政構造の悪化を招きます。財政の悪化を招くという恐れがあるのではないかという懸念も生じますけれども、そうならないように努力をいたします。
神戸市は先ほども申し上げましたように、震災の後の財政危機、市債の償還ができにくくなる。場合によってはできなくなるかもしれない。そうすると、当時の制度でいうと、財政再建団体への転落が危惧されるわけですが、こういう地方自治を失う選択肢ということはあり得ないということ、それを絶対に避けるということで、徹底した行財政改革が、笹山市政、矢田市政の下で進められました。その大きな眼目が職員数の削減でした。1995年から2025年まで、神戸市の職員を大幅に減らしております。2万1,728人から、2025年は約1万3,400人ということで、38%の職員を削減いたしました。これは全国の自治体の平均が14%ですから、倍をはるかに上回る、3倍弱ぐらいの職員を大幅に削減したわけです。同時に、全体的に減らすわけですけれども、必要な職員は確保するということで、例えばコロナ、あるいは子供の健康ということの重要な担い手である保健師につきましては増員をしております。「行革2025」、2025年度が最終年度になるわけですけれども、職員は全体で750人減らす中で、保健師は100人増員するということになっております。
行財政改革は、このように職員数の削減、それから投資的経費の抑制、そのほかの経常経費の削減などから行われてきたわけですけれども、その結果、神戸市の財政の健全性は確保されてきていると考えております。代表的な指標は将来負担比率と言われているもの、標準財政規模と比較してどれぐらいの実質的な将来負担があるのかという指標、それから、どれぐらい公債費を返しているのか、標準財政規模に占める自主的な公債費の割合(である実質公債費比率)、これは代表的な指標ですけれども、神戸は全体的には、この指標から見れば政令指定都市の上位にあると考えられまして、この両方が神戸よりも良好な都市は大阪、札幌、相模原、浜松の4市だけですから、全体としては財政の健全性は確保されていると考えています。今後、積極的な公共投資がしばらくは続くと思われますので、この数値は緩やかに上昇すると見込まれますけれども、全国平均以下、あるいは全国平均に近い水準を確保することができるような財政運営を心がけていきたいと考えております。
投資的経費の水準ですけれども、全体的には震災の後、もちろん急激に増加したわけですが、その後は低い水準で推移をしておりまして、2015年前後から、先ほど申し上げましたようにこれを増やしていくと。積極的に遅れてきたまちづくりを進めるということで、今回は久しぶりに1,096億円ということで、1,000億を超える水準になりました。この1,000億円代となるのは2002年度以降、23年ぶりということになります。
これが全体的な予算の額、水準についての御説明ですけれども、それでは令和7年度、どのような考え方で予算を編成したのか。つまり、令和7年度、神戸市の市政の基本的な方針は、この予算の中にどのように盛り込まれているのかということです。この4月、神戸空港は国際空港となります。このことは、神戸がかつてとは異なる新しい国際都市に進化していくことを意味します。そのような新しい国際都市となる可能性を手にするということを意味いたします。このチャンスを積極的に活用するということ、そして、その前提として、海外から神戸空港を通じて神戸、そしてその周辺に来られる方々を安全、確実にお迎えをする。そして、神戸に滞在していただくということ。そして、神戸空港を通じて海外との積極的な経済交流、文化、学術、スポーツなどの交流を進め、神戸経済の活性化を図っていく。こういう国際都市に進化していくための取組、これが1つの柱です。
もう1つは、そういう対応だけではなくて、新たな国際都市にふさわしい神戸のまちづくりを進める、神戸のまちの再生を図るということです。この再生という言葉を使った意味ですけれども、震災の後30年の間に課題としてあり続けてきたこと、そして今、私たちが目の前にある現実から目を背けることなく、それらの課題の解決につながるような形で神戸のまちをよみがえらせる。かつての国際都市としての神戸とはまた異なる、新たな国際都市にふさわしい神戸のまちをつくっていきたいと、そういう願いを込めています。
神戸のまちは、これは見方にもよろうかと思いますけれども、大きく言って3つのエリアに分けられると考えられます。1つは三宮、それから旧居留地、それからウオーターフロント、ハーバーランドにある都心です。もう1つは既成の市街地、そして、ここ半世紀ぐらいの間に開発をされてきたニュータウンですね。そして、神戸のかなりのエリアを占める森林と里山です。この3つのエリアを再生させる。この再生の取組を相互に関連づけながら行っていくというのが基本的な考えです。
都心の再生につきましては、2015年に三宮の再整備、それから、都市の再生のビジョンをつくり、これは着実に進められてきました。今、その姿が現れつつあるという段階です。もう実施段階にあります。それから、既成市街地、ニュータウンにつきましては、特にその周辺の郊外の土地のリノベーション、これもかなり積極的に進められてきまして、そのうち幾つかのエリアでは、その姿が見えつつあります。この都市の再生と既成市街地、ニュータウンの再生というのは、もちろん相互に関連づけられておりまして、都心については居住機能を抑制して、商業業務機能を重視したまちづくりを進める。ニュータウンにつきましては、これはしっかりと居住の受皿として、基礎インフラを賢く使うという考え方で再生をするという考え方ですね。そのような中で、この森林・里山の再生ということは、ここ数年散発的な努力が重ねられてきましたけれども、体系立った政策の展開は十分ではありませんでした。ここに今回、この都心の再生、既成市街地、ニュータウンの再生と関連づけながら、本格的に森林・里山の再生を行っていこう、こういう「3つの再生」を一体的に進め、持続可能な大都市を目指す、そのことが新しい国際都市神戸のまちづくりを意味する。そういう方向性を持ちながら、神戸のまちづくりを進めていきたいというのが基本的な考え方です。
まず、国際化への取組ですね。新しい国際都市に、神戸空港の国際化によってどう取り組むかということです。もう既に何回もお話しをしておりますように、4月18日には神戸空港の第2ターミナルビルが供用開始となりまして、定期便に近い形での運用が行われる国際チャーター便が就航すると。アジア5都市との間で就航するということになります。新しいターミナルもオープンをいたします。
この国際化に向けた対応方針といたしましては、1つは、この就航を確実に行う。受入れ関係を充実させ、快適で利便性の高い環境づくりを行っていくということです。海外の皆さんが神戸を訪れていただいて、そして、この神戸のまちを楽しんでいただく。市内での滞在、消費につなげて、何回も神戸に訪れていただくような対応をするということ。
もう1つの柱は、この空港が、更なる神戸のまちの発展につながる。短期的な取組だけではなくて、息の長いビジネス、そして観光につなげていく。そういう取組、人、もの双方向の流れを生み出していく、そういう息の長い取組を行っていこうということです。
そういう考え方のもとに、受入れ環境の充実といたしましては、インバウンドの受入れ基盤の構築をいたします。手荷物の預かり、配送サービスを導入する。多言語の対応を行うということ。重要なのは交通アクセスです。交通アクセスではポートライナーが非常に重要な役割を果たすわけで、全体としての輸送力は、この準定期便の就航によりましても間に合うわけですけれども、特に朝の通勤・通学時間帯は今でも混雑をしております。そこで、これを改善するということと、安全性を向上させるということで、新交通の三宮駅のホームを拡張いたします。2024年度(末)には工事に着手をし、2027年度末に工事が完了するように予算を計上いたします。それ以外には、ポートライナーを補完するバスの利便性を向上させるということで、朝のラッシュの混雑緩和のために、三宮駅、神戸駅南口とポートアイランドを結ぶ路線バスによる輸送力の増強を引き続き行います。具体的には、2025年度からは三宮の駅前のバス停を神戸阪急前からJR三ノ宮東口近くに移設をいたしまして、ポートライナー定期券所有者に発行している共通乗車証の対象バス停を拡充いたしまして、新たに新神戸駅を追加いたします。
双方向の需要創出といたしましては、海外ビジネスの交流を推進していくために、シンガポールに新たな東南アジアの拠点を新設いたします。市内事業者の海外販路の開拓の支援も強化をいたします。MICE施設の促進をするために、展示場などの施設の無料化、利用料を無料化する取組も行います。また、今後2030年には国際定期便の就航が予定をされておりますので、これをにらんだターミナル、空港の基本施設の在り方を検討いたしまして、整備の準備を進めていきます。
以上が、神戸空港の直接的な国際化をにらんだ対応です。
もう1つの柱が、先ほど「3つの再生」というふうに申し上げましたけれども、今まであまり取り組むことができなかった森林・里山の再生ということを本格的に行う。「森の未来都市神戸」プロジェクトを推進いたします。今、世界的に見て森林に対する関心が大変高まっております。世界を代表するグローバル企業が、このグローバル社会全体で森林再生の支援、気候変動をにらんだ森林の保全、再生に大変力を入れています。国内の企業もそうですし、国際機関も力を入れています。先日、世界銀行の国際会議に招待をいただきましたけれども、この世界銀行も森林、気候変動に対する森林強靱化プロジェクトを推進しています。アップル、マイクロソフトなどの代表的な企業も力を入れています。一方で、神戸市は海と山が都心に近接をしている。そして、先人たちから受け継いだ豊かな自然環境があるということ、これは神戸の強みであり財産です。しかし、残念ながら多くの民有林が放置されてきました。この森林・里山の再生を図っていくということであります。森林の再生ということは、グローバル社会の中でブランド価値を獲得する方途でもあると考えられております。そういうことで、緑の再生と創出を一体的に進める「森の未来都市神戸」、これを来年度から本格的に強力に推進をしていきます。
「森の未来都市神戸」のプロジェクトは2つの柱から成ります。
1つは、森林・里山そのものを再生するということと、森林・里山を再生する取組と関連づけながらまちの緑化を図っていく。まちの緑を飛躍的に増やしていくという取組になります。そのために森林の専門家であります黒田慶子副市長をトップとする本部をつくりまして、市民、企業、NPO、大学など多様な主体との協働により「森の未来都市神戸」プロジェクトを進めていきます。
取組のイメージですけれども、既に神戸ではこういう取組が始まっているわけですけれども、例えば、神戸にはこういう里山広葉樹林が豊富にあります。豊富にありますけれども、残念ながらなかなかかつてのように薪炭林としての利用がなくなりましたから、暗い森になって光が差さなくなって、生物多様性が失われているエリアも広がってきているというのが現状です。こういう取組を何とかしようということでプラットフォームが立ち上がり、また、森林整備の活動を支援するプログラムなどが推進され、多井畑西地区では子供たちの活動も広がっている。竹チッパーを使った竹林の再整備も行われるようになっていて、神戸の木を使ったこれは名谷図書館ですけれども、こういうふうに木を使った建物の整備や内装も進められています。
これをより本格的にやっていこうということで、里山広葉樹林の循環利用を促進する。資源がどれぐらいあるのかということをしっかりと調査をして木材を活用する、家具にする、クラフトにする、あるいはそれ以外のエネルギー利用を行うような計画を策定いたします。森林整備活動の支援制度を創設して、地域団体が行う活動に対して支援を行う。それから、どんどん広がり続けている竹林の管理・収集・活用も行うということ。神戸で備長炭を作っていこう、神戸に窯を作って備長炭を生産して、神戸のお店や周辺のお店でも使っていただく、そういう取組に取り組むこと。資源の有効利用ということで建物が解体されたときに発生する古材をリユースする取組を進めます。
こういう森林再生のための人材育成拠点、例えば、「KOBE里山SDGsベース」といったような拠点を整備するということ。子供たちの外遊びを推進すること、できる遊び場をつくっていく。あるいはそこを担っていただく人材を育成する、こういう取組、そして今まで進めてきた神戸登山プロジェクトも森林再生という見地からも強力に進めます。
まちの緑化につきましては、既に東遊園地が再生をされ、そして、この4月にオープンするGLION ARENAの周辺では、TOTTEIと呼ばれる緑豊かな空間が出現いたします。また、第1突堤、第2突堤の間の水域についても緑があふれる空間として整備をいたします。
引き続き、「こうべ木陰プロジェクト」を推進するととともに、都心におきましては、公共空間での高木の植栽を充実させて緑陰の形成をする。これは異常高温対策にもつながります。ポートアイランドの中央緑地軸、あるいは主要街路における街路樹の再整備を行っていくこと。それから、公園の樹林環境につきましても、公園の生い茂っている木を間伐することによる明るく見通しのよい空間づくり、これも適地を選びながら行っていきます。
また、西神戸ゴルフ場を産業団地として造成をいたしますけれども、ここから発生する樹木につきましても可能なものは移植をいたしまして、シンボルツリーなどとしても活用いたします。
以上が新しい国際都市神戸をにらんだ空港を活用した国際都市への取組、それから、都心、既成市街地、ニュータウン、そして、里山・森林の再生、これによる神戸の新しいまちづくりというものを行っていく。
以上、2点につきまして、予算の中の重要項目として説明をさせていただきました。
以下は予算編成における6つの柱に沿いまして、主要なものを御説明いたします。
まず、第1番目の柱、「くらしと安全を守る」部分ですけれども、震災30年を踏まえた災害対応力を向上させるための予算です。
神戸市は震災の後、あのような甚大な被害が出るという事態は絶対に繰り返してはいけない、そういう強い信念のもとに、つまり都市の繁栄、都市の発展というものは災害に強い強靱な都市基盤の上に初めて成り立つという信念のもとに様々なプロジェクトを進めてきました。今後は近年発生した、例えば能登半島地震などの状況を踏まえて、災害対応力を向上させる必要があります。
1つは、危機管理局を設置いたします。また、避難所の(良好な居住)環境を確保するために間仕切りテント、簡易ベッドを1万基追加配備するとともに、非常用電源の更新などを行います。トイレカーも新たに導入をいたします。震災30年の取組として、レジリエンスセッション、グローバルカンファレンスなどを行います。
暮らしの安全・安心を守るという観点から防犯カメラを増設いたします。通学路、駅周辺に整備を行ってきたわけですが、東京における闇バイトの強盗事件などを踏まえて住宅地などにもカメラを設置いたします。公園の樹木、街路樹については、続けて倒木があったという状況を踏まえて緊急点検を行いました。こういう事故を踏まえて、公園、それから道路で倒木を防ぐために公園や道路法面の樹木、街路樹を点検し、リスクが高い樹木は撤去をいたします。このために2月補正と合わせまして11億6,000万円の予算を計上し、積極的に倒木の撤去を行います。
銭湯については神戸市が力を入れてきた分野です。これはやはり特にシニア世代などの方々の健康を守るということ、それから、世代を超えた交流の場、コミュニティーの場としても非常に重要な役割を果たしているという見地から、これまでも既存の設備の改修、あるいは子供と一緒に銭湯へ行く場合の割引などを行ってきました。しかし、これを持続可能なものとしていくためには、大規模な施設改修ということも必要ですので、最大3,000万円を神戸市が補助する新たな大規模設備改修補助制度を創設いたします。
「人間らしい温かい街を創る」、子育て支援施策の中で高校生の通学定期券補助(の大幅拡充)を昨年度スタートさせました。市内の高校に通う市内の高校生については通学費を全額無料にするということにしたわけであります。神戸市は基礎自治体ですから、これは市内の高校の持続可能性を確保している、そういう目的も併せ持った制度ですから、市外につきましては1万2,000円を超える部分の半分を補助するという、そういうふうにかなり差を設けました。これは基礎自治体の政策ですから、市内と市外を分けるということは維持しなければなりません。本格的なこの問題への対応はやっぱり兵庫県に行っていただかなければなりません。
もともとこれは、大阪府と兵庫県との間で授業料負担に非常に大きな差があるということに起因する、神戸市としてはやむにやまれぬ対応であったわけですね。今、高校授業料については与野党間で協議が行われていますから、その動向はもちろん注視をしたいと思いますけれども、仮にその結果、大阪府と兵庫県との間で格差が残るということ、このことは神戸市を含む兵庫県内から大阪府内へ子育て世帯の流出を招く恐れがありますから、これは兵庫県でしっかり対応していただかなければならないというのが神戸市の基本的立場です。
この点ついて、兵庫県においては私学の関係者を交えた検討の場をつくると言われておりましたけれども、先日開催されました兵庫県と市・町の会議では、その点についての説明が全くなかったんですね。これは大変残念でした。やはり兵庫県はもっと問題意識を持って、大阪府と兵庫県との間の授業料格差について真剣に取り組んでいただかないと、これは本当に困った事態になると思います。
そういうことを前提といたしまして、しかし、神戸市の高校生世帯から見れば、市外と市内の間にやっぱり大きな差があるということについては、かなり様々な意見もいただいておりましたので、今回、市外について1万2,000円を超える部分の2分の1という1万2,000円という基準額を撤廃いたしまして、実際に必要とされる通学定期代の半分をですね、ですから、大幅に補助対象が拡大されることになりますが、これを拡大することとなりました。あと、産後ケア事業の受け付け時期を前倒しする。あるいは病児保育を拡充する。夏休みの学童保育ニーズ、受入れ施設を20施設から50施設に大幅に拡大する、こういう対応も行います。
このほか、学校図書館での放課後居場所づくり、子供の健康ということから見れば、歯の健康は非常に大事ですから、フッ化物洗口による小学生のむし歯予防。洗口液を配付して家庭の中で口をゆすいでもらう。それから、虫歯の割合が高い学校を重点的に外部人材を活用して、集団洗口してもらうという取組。あと、スケートボード広場の増設などを行います。そのほか、まちなか自習室を設置するといった学びの環境整備を行います。
KOBE◆KATSUにつきましては、これは教育委員会と市長部局が連携して対応していくための予算を計上いたしました。KOBE◆KATSUにつきましては、教育長をはじめ教育委員会から何回も説明が行われていると承知をしておりますが、教員の負担軽減のために行うわけではありません。今の中学校の部活というのがもう既に持続可能ではない、このままではもたないということ。それから、中学生の子供たちが放課後に豊かな時間を過ごしていただくためには、部活動に代わる対応が求められているということ。そして、豊かな時間を過ごしていただくために、神戸にはスポーツやあるいは文化・芸術、非常に特技を持った方々がたくさんいらっしゃいますから、そういう方々に積極的に参加していただいて子供たちに指導をしてもらう、あるいは見守りをしてもらう、そのことが結果的に教員の負担軽減につながるという考え方で進めているわけです。これはやはり強力に進めていかなければなりません。
そのために新年度予算におきましては、KOBE◆KATSUクラブの募集、相談対応のための予算。第一次募集、これは1月16日から始まって2月16日まで募集をしておりますが、既に620のクラブから応募があるということで大変力強く感じています。
予算の内容といたしましては、先行実施する新しい種目の保険料負担、あるいはホームページによる情報発信、中学校の施設を利用していただくための環境整備として、日没後の活動を想定したグラウンドなどへの簡易照明の設置、あるいは文化施設の環境整備として、防音対策を備えている文化センターで吹奏楽の活動の場を提供する。こういうような支援のための予算を計上しております。
3番目のカテゴリーが「持続可能な神戸を創る」、先ほどの神戸のまちの再生の2番目のカテゴリー、郊外あるいはニュータウンの活性化ということのために、郊外の駅のリノベーションを積極的に進めてきました。また、都心と既成市街地、重なり合っているところがありますが、神戸駅や兵庫駅や地下鉄の長田駅、新長田、こういうところのリノベーションも進めております。これがかなり姿を現してきておりまして、これから計画を具体化させるものを含めて、駅周辺のリニューアルを積極的に進めていきます。
既存の資源、インフラを整備するという考え方が駅周辺のリノベーションにあるわけですけれども、既存の資源ということで言えば、空き家、空き地がまさにそうです。神戸市はこれをこれまでも積極的に進めてきておりまして、使える空き家は活用する、老朽危険家屋は撤去するという考え方で、新しいソフト施策なども含めた施策の充実を行います。
郊外のリノベーションということから見れば、住民の皆さんの足を確保するということが必要で、あるいは通勤・通学環境の改善ということからも、バスの停留所の上屋ベンチの整備、日差しや雨をしのぐための整備、それから地域コミュニティー交通の導入・運行支援なども積極的に行います。神戸は関西でも有数の農業都市で、農業の振興ということと、それから農村地域の活性化ということを同時に行わなければなりません。同時に人手不足が進行していますから、スマート農業を推進するためのスマート農機の購入補助を拡大するということ。ラジコン草刈り機のレンタルの実施なども行います。有害鳥獣、外来生物対策も里山地域の活性化ということでは、地味だけれども不可欠な取組です。
総務省が地域おこし協力隊という制度を地方創生、地域の活性化、移住促進という目的で行っておりますが、指定都市は対象外になっております。神戸市は広大な農村地域を抱えていますから、国の支援は受けられないけれども、神戸市単独の施策として地域おこし隊、神戸地域おこし隊の隊員を募集し、隊員に幅広く活躍をしていただいています。これも大幅に人数を拡大して、神戸への移住、そして、神戸の地域の活性化に取り組んでいただきたいと思っています。
持続可能な地域循環型社会ということから見れば、竹林の管理、竹林の収集・活用ということ。もう1つは、脱炭素先行地域に環境省から指定をされましたので、これを活用したポートアイランドにおける再エネ・省エネ設備への支援を行います。
4番目は、活気と魅力あふれる神戸の創生です。
市内産業の活性化という観点から、神戸市産業振興財団と神戸いきいき勤労財団を統合いたしまして、企業支援と就労支援、これを一体的に行うことといたします。この4月、新財団を発足させまして、7月にはいきいき勤労財団の事務所を神戸市産業振興センターに集約をし、一体的に行うことといたします。
新たな起業・創業支援といたしまして東京事務所を移転し、様々な企業支援あるいは民間企業の方々とのディスカッションや、イベントを行う場所として活用をいたします。神戸での起業希望者に対する起業・創業プログラム、これを東京と神戸で一体的に行っていきますし、また、新たなスタートアップ支援法人の設立につきましても、検討をしていきます。神戸はともすれば行政主導でスタートアップ支援を行ってきていて、うまくいってきた面もありますけれども、これをより民間の市内企業と連携した対応にしていきたいということで、新たな法人をつくりたいと考えております。
このインキュベーション機能と言うと、どうしても都心が中心になるわけですけれども、神戸の場合には、新長田のシタマチスタートアップの取組を進めてきましたが、新たに湊川エリアでもそういう取組をしていこうということで、インキュベーション施設をパークタウン、湊川パークタウンを念頭に設置をしていきたいと考えています。
万博への対応につきましては、夢洲へのクルーズ体験、市内の子供たちを対象とする夢洲体験クルーズを実施するということ。経済界と連携をいたしまして、ビジネス交流も行います。万博来場者の神戸への誘客のキャンペーンなども実施をいたします。
六甲山・摩耶山の活性化といたしましては、六甲山・摩耶山、六甲山は特に大分変わってきました。多くの遊休化した保養所、別荘などがありましたけれども、まだ完全ではありませんけれども、それらが生まれ変わりつつあります。道路環境あるいは水道、通信環境も大幅に改善をいただきまして、六甲山に新たなオフィスやコワーキングスペースなどが生まれつつあります。さらに、森林の再生ということの一環でもありますけれども、登山道の整備を促進する。また、登山道のトイレの環境などの整備も行います。
六甲山・摩耶山への登山道の入り口に当たる諏訪山には、トレイルステーション諏訪山を整備いたします。また、森林植物園の中にはマウンテンバイクコースも試験的に設置をいたしまして、SDGsにふさわしい山の楽しみ方としては、マウンテンバイクが非常に有望で、これは国際的に見ても非常に幅広く行われておりますので、こういうコースを広げていきたいと考えています。摩耶山のにぎわい創出ということから見て、新たなロープウェーの構想ということをこれまでも発表し、市民の皆さんに議論をしていただいてきました。これにつきましては、さらにこの導入検討調査を進めていく予算も計上しております。
スポーツ・芸術・文化につきましては、神戸マラソン、今年はいよいよコースが明石に折り返し地点が延長される。そして、フィニッシュ地点は神戸ハーバーランドに変更をされることになります。これによって走行環境が大幅に改善をされる、コースとしての魅力も大幅に増加をするということで、海外ランナーの増加も見込まれます。そのための経費。
それから、来年度は、神戸国際フルートコンクールの開催年であるわけですけれども、これと併せた、ジャンルにとらわれない音楽フェスティバルとして、「KOBE国際音楽祭2025」を開催いたします。
アーティストの支援も強化をいたします。
5番目の新しい国際都市神戸を創るでは、まず、都心・三宮の整備になりますね。今、もう大きく神戸の都心が変わりつつあります。東遊園地、ポートタワーはもう変わっている。阪急ビルですね。あと、それぞれ、今後はGLION ARENA、新バスターミナル、それから、三ノ宮のJRの新駅ビル、こういうものが次々にオープンをしていくことになります。
これを地図で落としますと、神戸の三宮、そして、フラワーロードを南下して、ウオーターフロント、ハーバーランドのこの一帯がこれから大きく変わっていくことになります。これを確実に進める、つまり、これは実施段階の予算、これを確実に計上いたします。
これに続く活性化が求められているのは、ポートアイランド、六甲アイランド、HAT神戸で、これはより本格的な検討を進める必要がありますが、まずポートアイランドについては、リボーンプロジェクトを今推進中です。これはかなり時間をかけて、地元の皆さん、そして、大学、様々な皆さんに、もちろん地域住民の皆さんに参画をしていただいて、ワークショップなども頻繁に行いながら進めていきたいと考えておりますけれども、しかし、やれるものはしっかりやっていこうということで、社会実験のほかに緑化をする、青少年科学館のリニューアルをする、こういう取組を進めます。
六甲アイランドについても、マリンパークの再整備、六甲アイランド公園の再整備などを行いますし、HAT神戸についても、通年型のアイススケートリンクが完成することになりますから、これを活用したスポーツ機会の創出、あるいは市営住宅の空き空間を活用した都市型の農園モデル事業などを行います。
6番目のカテゴリー、DXを活用した市民参画ですね。行政施設の機能強化ということで、六甲アイランド、これは六甲アイランドの活性化とも関係しますが、出張所を設けてマイナンバーカードの関連手続や、あるいはスマホの相談窓口、これは非常にニーズが高いものなので、そういう出張所を開設する。
それから、歴史公文書館の整備、これもかねてより進めてきましたけれども、来年の6月に開設ができるように必要な予算を計上いたします。
北区での新たな建設事務所、これは2027年度に開設できるように、着実に工事を進めます。
以上が、来年度予算の特に重点施策として考えている事柄を御説明申し上げました。神戸がかつてとは異なる新しい国際都市として、進化をさせるための攻めの予算として計上をさせていただくことといたしました。
この予算につきましては、間もなく開会される神戸市会において提案をしっかりと説明させていただき、しっかりと御議論をお願いしたいと思っております。
私からは以上です。
質疑応答(発表項目)
記者:
まず、前半に話があった財政状況についてお伺いします。これまで行財政改革に取り組んできて、主な軸は職員定数の削減だったという話もありました。今年で震災から30年を迎えますが、これまで続いてきた行財政改革をどのように評価されるのかお伺いしたいのと、あとは歳出のほうを見ますと、投資的経費が23年ぶりに1,000億円を超えたということですけども、今後、神戸空港の国際化も控えまして、財政的に厳しい、我慢する時代を経て、今こうやって投資的経費、投資に回せていることについて、所感をお伺いしたいです。
久元市長:
やはり30年前に突然の震災があり、神戸市政はとにかく必死で危機と戦う災害応急対策、それから、災害復旧に取り組んだわけですけれども、その後、災害復興も含めて、その財源を確保するという意味で市債に頼らざるを得なかったわけですね。これは私自身、東日本大震災への対応を総務省におるときに経験しましたけれども、その当事者でもあったわけですが、全然国の財政措置が違っていた。そのために、大半の財源を市債に頼らざるを得なかった。
これが神戸の財政状況から見れば、極めて償還能力を超える事業をやらざるを得なかった。これが非常に困難になる。先ほども申し上げましたけれども、償還ができなくなると、これは当時の制度で言うと、財政再建団体にならざるを得ない。このことは財政自主権を放棄するということで、地方自治を失うことを意味するので、神戸市、日本を代表する大都市として絶対にこれは避けなければいけないということで、先ほど申し上げたような行財政改革、断固たる決意で遂行された。これは笹山市政と、特に矢田市政の12年間の間で、これが行われました。
これは相当困難を伴ったと思います。職員の皆さんにも非常に大きな苦労があったと思うんですが、しかし、そのかいがあって、もちろんこの間も神戸医療産業都市など必要な事業を行われましたし、災害強靱化のための事業も、例えば大容量送水管でありますとか、下水道を使ったポンプ場の整備など、災害対応力の強化のための事業は行われましたけれども、未来を見据えたまちづくりということは、これは取り組むことができなかった。
それが取り組むことができるようになったのは、やはりこの間の行財政改革によって、神戸市の財政状況が大幅に改善をした、そのことが、その後、ここ10年余りの間に、神戸の新たなまちづくりを進めることができる素地になったのではないかというふうに思います。
このことは、同時に少ない人数でも対応できるという、そういう経験というものが重ねられてきたということを意味すると思います。個々の職員の皆さんや、個々のセクションには大変大きな御苦労をかけていると思いますが、しかし、例えばコロナの対応でも、少ない人数でもかなりのことができたというふうに思います。例えばワクチン接種は大都市の中ではトップクラスのスピードでしたし、それから、コロナ患者の感染者を確認するための独自のDXを使った取組、それから、特別定額給付金の給付も大都市の中でトップクラスの早さでした。
これはやはり職員の皆さんが知恵を出して、少ない人数でスピード感を持った仕事をすることができるというパフォーマンスを示していただいたということだと思うし、今後人口動向、出生数の推移を見ても、これから企業も自治体も国も、もう人員を大幅に増やすことができない時代ですね。そういう中にあって、神戸市はこういう人口減少時代にふさわしい行政運営ということの実績を積むことができていたので、そういう経験あるいは思いというのは、今後さらに加速する人口減少時代の中で、神戸市の行政運営を行っていく上での大きな武器ということになっているのではないかというふうに思います。
すみません。2番目の御質問をもう1回繰り返してもらっていいですか。
記者:
そういう厳しい時代、財政的に我慢の時代が続いたことがありましたけども、今、神戸空港の国際化も控えて、まちづくりのほうに投資ができるということについて、思いを改めてお伺いしたいです。
久元市長:
神戸空港の国際化というものが、新しい国際都市を目指す上で、大きなチャンスとなる。そういうチャンスを私たちは獲得することができたということだと思うんですね。ですから、これは定期便に近い形で国際チャーター便が運航できてよかったよかったではなくて、これをどううまく活用して、神戸の経済の活性化につなげていくことができるのかということだと思いますね。
やはりどうすれば海外に打って出ることができるのかということ、それから、海外の企業やあるいは大学や研究機関との間の交流というものを、産学官の連携によっていかに強力に進めることができるのか、そこが知恵の出しどころではないかなというふうに思います。神戸市政はやはりそういう意味で、ある意味でコーディネーターの役割、あるいはプラットフォームの役割をしっかり果たして、経済界やあるいは理研などの研究機関、それから大学との連携をいかにうまく進めることができるのかという、そこが問われているというふうに思います。そのためにやらなければいけないことを全力でやっていくということだと思います。
記者:
前段のお話で、人口減少社会にというお話もありましたけども、財政の持続可能性についてお伺いします。今後、人口減少、少子高齢化で、一般論としても税収の減少ですとか、あとは社会保障費の増加とかで財源、財政が厳しくなるということが予想されます。先ほどのお話でも、今後積極的な公共投資が続いていくというお話もありましたけど、この部分と、あと財政的な持続可能性というところをどのようにして両立させていくのか、お伺いしたいです。
久元市長:
まず、今後の投資的経費の見込みは、三宮都心については既に計画が確定していますから、これは予定どおりに進めるということ。それから新たな投資というものは、例えばHAT神戸、それからポートアイランド、六甲アイランドで生まれて、しなければいけないプロジェクトというのはありますけれども、これについては既に都市基盤というインフラをしっかりしていますから、あとはどういう新しい要素をこれに加えるかということを考えて、投資規模ということも慎重に見極めながら新たな施策を考えていくということだろうというふうに思います。
全体としては、先ほどの将来負担比率、それから実質公債費比率を見ましても、神戸市の標準財政規模からいって、これがものすごく上昇するということはなかなか考えにくいです。既に先ほど申し上げたような投資規模というのは大体分かっていて、今後新しく増えることについて、これ、しっかりと費用対効果を考えながら個々の事業を精査し、そしてどうすれば一番費用対効果が上がるのか。費用対効果という意味は、どうすれば高い経済効果が見込まれるのかということだと思うんですよね。そういうことを考えながら事業を進めていく。投資規模というものも決めていくということを考えれば、そしてこのリターンというものも考えながら投資を行っていくと、この分母である標準財政規模がこれから大きくなっていくことを目指すということを、そういう投資判断と財政運営を行えば、この指標が大きく上がることはなかなか考えにくいと思いますし、そうならないような財政運営をしなければいけないというふうに思います。
こういう指標に大きく影響を与えるのは扶助費と人件費なんですよね。扶助費はなかなかコントロールしづらいです。扶助費は例えば生活保護、それから介護保険給付、医療費、高齢者福祉、障害福祉などですね。これは国の制度で決まってくる部分もありますから、なかなかコントロールしづらいわけですけれども、こういう分野については、これは神戸市の対応力に限界あるということではなくて、どうしたらみんなで地域社会を支え合えるのか。孤立とか孤独が広がっているという面もありますから、独りぼっちになっている人をどうやって減らすのか。どうしたらコミュニケーションの機会をつくれるのか。一例を挙げれば、独り暮らしの高齢者世帯がすごく増えていますね。こういう方々がずーっと家にいて、1日中テレビを見ていれば、足腰が弱る。フレイルが進行する。場合によったら認知症になる。認知症が進行する。そうならないように神戸市は認知症神戸モデルをつくって推進しているわけですけれども、こういう取組をより企業や大学や、そして多くの市民の皆さんに関わってみんなで支え合うような地域社会というものをどうつくっていくのか。そのことが結果的に扶助費に対して、扶助費を減らすためにそういうことをやるというのではなくて、そのことを進めることによって扶助費に少しでもいい影響が、その増加を抑えることができるようにするということだろうと思うんです。
もう1つは人件費です。人件費は、これ、かなりのペースで職員数を減らしてきました。今後ともこのペースで職員数を減らすかどうかというのは、今の行革プランが2025年度が最終年度ですから、これから考えていくことになります。これから考えなければいけませんけれども、少なくとも職員数を増やすという選択肢はないのではないだろうかと思います。
最近の議論の中で、日本の公務員の数が諸外国に比べて少な過ぎる。もっと増やしてもいいという議論がありますけど、私はそうは思わないです。というのは、諸外国に比べて速いペースで人口が減っていきます。そもそも増やしたいと思っても増やせるかということがあります。例えば神戸市でも技術職員が募集人員どおりに集まらない。これは、あちこちで起きていきます。そうすると、増やしたくとも増やせないという時代になってきているということを前提に考えなきゃいけない。
そうすると、少数でいかにパフォーマンスの高い仕事の成果が上げられるようにするのかということですね。1つはDXを進めるということなんですが、DXは万能ではありません。どうしたら職員の皆さんが面白い仕事ができるようにするのか。そして神戸市に限らず、それぞれの自治体、それぞれの企業に入ったら自分自身をどう成長させていくのかということができる、成長環境というものを用意していく。そのことによって高いレベルの仕事をやっていただく。そういう環境をしっかりつくっていくということ。職員同士のコミュニケーションも活発にするための取組ということも必要だと思いますから、そういうことによって職員の皆さんの士気と、そして費用対効果を上げていく。こういう地道な取組も必要ではないかというふうに思います。そのことが結果的には、先ほど申し上げたような指標の増加というものを少しでも抑制することができるのかということにつながっていきます。
記者:
新年度の予算についてお伺いします。特に森林の再生についてお伺いします。先ほどのお話の中で、森林の再生がグローバル社会の中でブランド価値を獲得していくというお話がありました。このブランド価値というのが具体的にはどういう観点で、どういった方に感じてほしいのか、ブランド価値を高めた先にどういうことがあるのか、その重要性についてお伺いしたいです。
久元市長:
やはり、先ほど申し上げましたけれども、この森林の再生というところにグローバル企業、あるいは世銀などの国際機関、あるいはかなりの大都市が森林の再生ということに目を向けています。まずは自らの都市の緑というものをいかに増やすのかということですね。これは、例えば最近ではオリンピック・パラリンピックを行ったパリは非常に力を入れている国ですよね。これは気候変動を意識した取組です。
緑あふれる都市というのがブランド価値を生んでいるという典型的な例がシンガポールです。シンガポールはアジアを代表する国際都市ですけれども、これはもうかなり早い段階で都市の緑化、緑をいかに増やすのかということに取り組んできましたね。私も一昨年だったでしょうか、シンガポールにごく短期間でしたけど、見に行ったのは、この緑化の取組というものをぜひ見たいということも1つの動機でした。非常に熱心に取り組んでいて、本当にまちの中に至るところに緑がある。植物園の園長にもお会いしましたけれども、ものすごく高い専門的なレベルの職員がたくさんおられるということで、ぜひこのシンガポールの植物園の園長を神戸にお招きしたい、レクチャーもしていただきたいということで今、検討を進めているところです。
やはりそういう森林を再生する、緑を増やす取組というのが既にグローバル社会においては価値を獲得している。大都市においてもそういうふうに取り組んでいる中にあって、神戸は海と山がある。昨年、議決をいただきました神戸の基本構想、「神戸は海と山に囲まれた都市です」という文言から始まるんですけれども、海と山に囲まれた港町という、そういうような趣旨で始まるんですが、同時に人間らしい温かい都市を目指すということも言っています。そういうような大きな方向性の中で、神戸には海があり、山があり、そしてこの山は六甲山などの森林・里山から構成される。これを再生していくというのは、神戸の財産に改めて目を向け、磨きをかける。そして、このことは、ほかの都市とは違うありようで森林の再生を行う。ほかの都市とは違うアプローチで森林を再生するということが、共通理解となっている森林の再生、そしてそのことが取りも直さず気候変動への橋頭堡にもなるという中で、神戸の取組というのは意義があるのではないか。そして、そのことはブランド価値を持つのではないだろうかというふうに思っております。
それで何につながるのかというのは、これは一方的に行政が考えることではなくて、これは今までなかなか取り組むことができなかった政策の内容をある意味で提案しているということを意味しますから、この提案に対して市民の皆さんがどういうふうに反応していただけるだろうか。企業の皆さんがどう対応していただけるだろうか。あるいは大学など、神戸にはたくさんの大学がありますから、大学の研究者の皆さんや学生の皆さんがどう対応していただけるのかということにもかかってくるのではないかと。そういう皆さんとの間でディスカッションをしっかり重ねて、そしてこの我々の取組というものをどう進化させていくのかということが我々のやらなければいけないことではないかというふうに思います。
記者:
今、今後何につながるのかというのは一方的じゃなくて皆さんと話しながら、ディスカッションを重ねながらというお話がありましたけども、一方で、こうすることによって市民の皆さんにはどういうふうな還元があるのかというのは、行政としてどのように想定されているでしょうか。
久元市長:
市民の皆さんにとって原生的利益というものはあまりもたらされないかもしれませんね。一人一人にとっていくら得をするとかしないとかということではないかもしれません。しかし、私たちはそういう一人一人に還元される原生的利益というものだけで生きていけないということは事実です。
今、神戸は大阪、京都よりも夏の最高気温が低いと言われていて、神戸は海があり、山があるから比較的夏は過ごしやすいかな。冬も比較的温暖と言われてきましたけど、その状況が大きく変わってきていますね。これは、一人一人に還元される原生的利益ではなくて、みんなが共通して享受することができる利益というものが損なわれてきているということだろうと思うんです。これはなすすべがないというふうに諦めるというのも1つの選択肢ですけれども、そうではなくて、それに対してやはりみんなで力を合わせて立ち向かおう。気候変動というのを食い止めていくためにはどうすればいいのかというアプローチは、いろいろと様々な機関が提言をしています。あと、行政を含め、市民の皆さんの選択肢は、そういうものに背を向けているのか、あるいは、みんなで力を合わせて現実というものと向き合うのかということだという気がします。そのことを共通利益として考えていただけるのかどうか。そこは、我々は、それはみんなでやらなければいけないということで、その提案に対してしっかり議論をして共通理解を深めていくということが大事ではないかというふうに思います。
記者:
念のため確認なんですけど、今向き合っていかなきゃいけない現実というのは、念頭に置かれているのは気候変動に対してということでよろしいでしょうか。
久元市長:
気候変動の影響というものにどれだけ貢献できるのかということもありますが、しかし、気候変動によって現実に起きているのは夏の異常高温。夏の異常高温を少しでもしのげるような対策というのが「森の未来都市神戸」の中には組み込んでいます。これは木陰をつくるということであり、あるいは、せせらぎをつくるということであり、あるいは竹チップや木材チップを使って舗装の内容をより変えていくとか、いかに地表温度の上昇を抑えていくのかということですね。
神戸市はこういう取組をしなければいけないわけですが、しかし、同時に市民の皆さんにも、この面での関心が高まっていることは事実です。例えば御影高校の皆さんは、この竹チップを使った舗装ということを考えたらどうかという提案がありました。これは早速、それを使わせていただくことにして、先日オープンした磯上公園の中にもこれを使いました。こういうことを広げていくということですね。
こういう異常高温をいかに減らすのか、あるいは神戸に賦存する森林資源というものをいかに上手に活用するのかということは、いろんな提案をいただくようになってきているんですよね。ですから、そのことは非常にありがたいことで、せっかくいただいた提案というものを行政としてうまく生かす。そしてもっともっといろんな提案をしていただいて、森林の再生ということにつなげていきたいというふうに考えています。
記者:
最後の質問なんですけども、新年度の事業として、森林に関しては推進本部を設置して、拠点の整備ですとか、かなり始まりの部分かと思います。森林事業はなかなか短期で結果が出るわけでは、かなり長期的な視点が必要になるかと思います。久元市長の任期も残り10か月、9か月ほどですけども、どうやってこの長期的な事業を進めていかれるお考えでしょうか。
久元市長:
神戸市の市政の基本方針というのは持続可能性です。持続可能性ということを考えて、例えばタワーマンションの規制というのも、目先の人口を追い求めるのではなくて、長い目で見た都市の持続可能性ということを考えようと、そういう都市の持続可能性ということを考えたときには、分譲型タワーマンションというのは持続可能ではないのではないかという問題意識を持っております。
森林の再生もそうです。これも短期間に効果が出るものではなくて、時間がかかるでしょう。それからポートアイランド・リボーンプロジェクト。これも時間をかけて進めようとしております。これは任期が、私の任期は11月に終わるわけですが、11月の任期中に終わるものしかできないとは私は考えてはいません。これは今までの市政もずっとそうだったと思います。
初期の神戸市政は、水道を布設するということが非常に大きなミッションですよね。この水道の布設ということと、その当時荒れ果てていた神戸の六甲山の再生ということは深く関連づけられていました。これは相当時間がかかるということを覚悟して初期の神戸市政は取り組んだわけです。これは市長だけではなくて、その当時の神戸市会も、これにさんざん議論をして取り組んだ。やはり都市の持続可能性というのは、そういう中長期的な視点があって、そしてそういう中長期的な視点に基づく議論が行われ、それが具体化されることによって今の神戸が生まれてきたと思います。そのことがなければ、短期的なことしか考えないということであれば、今の六甲山の姿というのはなかったと思うし、布引貯水池もできなかったと思うし、今の神戸にはなれなかったと思うんです。ですから私が11月で市長でなくなれば、新しい市長の下で、これを全部御破算にしますということは1つの選択肢です。それはそのときに議論していただければいいのではないかというふうに思います。ただ、私はこの持続可能性ということについて、多くの方々の理解を得て、仮に市長が代わることがあっても、これを続けていただきたいという希望は持っています。それはあくまでも希望です。
記者:
ちょっとまた全ての、大枠の予算のお話で何点かお伺いします。まず、今回の予算編成、いろいろ打ち出すメッセージは、先ほど、新しい国際都市として進化するための攻めの予算だということもありましたが、予算編成、バランス等苦労された点と、この攻めの予算というところで、これを踏まえて、どんな都市を目指すのかというのを、もう少し具体的にお願いできればと思います。その2点よろしくお願いします。
久元市長:
どんな都市を目指すのかというのはまさに、新しい国際都市神戸を目指すということです。新しい国際都市神戸というメッセージを立てたのは、かつて神戸は日本を代表する都市でありました。それは我が国を代表する国際港湾であり、世界を代表する国際港湾であったからですね。そのことが、神戸を当時1960年代に、世界を代表する国際港湾都市として、あるいは我が国を代表する国際都市に押し上げたわけです。その時代を懐かしんでいるだけでは駄目だというのが基本的な認識です。時代は大きく変わりました。
これは震災の前に、神戸は国際港湾都市としての地位を失っていたと思います。それは神戸だけの責任ではありません。諸外国が、例えば韓国が釜山や仁川に、中国が天津や上海に、あるいは香港、シンガポール、こういう都市国家が国家プロジェクトとして国際港湾都市として成長していく、国家プロジェクトとして港湾の整備をしていく中で、我が国は国土のバランスの取れた発展という観点から、地方港湾の充実をするという考え方に、相対的に横浜や神戸などの、かつての、その時点における、あるいはそれ以前の国際貿易港に対する投資というものが諸外国に比べて遅れることになりました。これは、貨物取扱高を見ても歴然としていて、神戸は震災の前に国際的な競争力というものを失っていたと思います。そういう中で震災に襲われて、港湾は壊滅的被害を、その後、関係者の必死の努力によって神戸港は復活しましたけれども、かつて、世界を代表するニューヨークやロッテルダムに匹敵するような地位を回復することはできなかったんです。これはできるはずもなかったんです。それは国の政策とも関連していますからできなかったわけです。
それともう1つは、人や物の流れ、特に人の流れが港湾から空港に変わっていったと。1960年代に国が神戸沖に空港をつくろうという提案をしたときに、神戸市民はこれを受け入れなかったわけです。そのことによって関西国際空港が誕生をして今の関空があるわけです。そういうことを考えれば、それを前提として今、神戸空港ができて、そして関係者の努力によって神戸空港が国際空港になるということは、これは、昔に比べれば相当様相は違うけれども、神戸には港湾がある。そして苦労してつくった、関空に比べれば小規模ではあるけれども神戸空港があって、これが国際空港になる。つまり国際港湾と国際空港があるということ、これは神戸にとって非常に大きな財産で、それを手にすることが我々はできたわけです。ですからこれを活用して、かつてとは違う、我が国を代表する国際都市として進化をすると。このことが今の神戸市としての大きな方向性だろうというのが全体的な方向です。
これを具体化するための施策というのは先ほど説明した各般にわたるものなので、説明は繰り返しませんけれども、そういう基本的な方針のもとに、国際交流あるいはグローバル経済社会への対応と、内にあっては神戸のまちの再生ということをそれぞれのエリアごとに考えていきながら行っていく。そのことによってグローバル社会の中で名誉ある地位を獲得していくということ。これが大きな来年度予算の方向性です。
記者:
子育て周りでお伺いしたいんですけども、高校定期券の無償化の拡充であったり、保育料の軽減など、いろいろ子育て世帯向けの取組というのを多く、今回も打ち出されておりますが、変わらず阪神間、大阪、明石の間では、各自治体が子育てに向けたいろんな政策を打ち出されているというところですが、市長として、ほかの地域とは異なる、神戸で子育てする魅力というのを、改めてどのようなものかお話しいただけますでしょうか。
久元市長:
一言で言うと、すくすくと成長できる環境がもともとある。そしてそれを生かす取組ということをこれまでやってきて、かなり魅力とすることができてきたということだと思うんです。つまり、女性が結婚し、妊娠をし、赤ちゃんが生まれ、そして、大体高校を卒業するまでの間の切れ目のない支援ということを、神戸市が力を入れてきて、それはかなり実を結んできた。そして、神戸では子育てしやすいまちだというような評価も、かつてはそうではなかったんですけれども、次第に定着しつつある。そのことは、やっぱりすくすくと成長できるような環境ということを、これは行政だけではないけれども、子育てに携わる方々が知恵を出し合ってつくり上げてきたということ、地道な努力が表れてきているということではないかなと思います。さらにこれをよりよいものにしていく上で、今年度の明確な視点は、子供たちが神戸の自然の中で伸び伸びと体を動かし、そして神戸の自然のすばらしさということを満喫してもらえるような、そういう取組を加えてきているということです。
残念ながら、日本の子供たちの体力は低下し続けています。神戸の子供たちの体力も、年代によって若干違いがありますけれども、全国的に比べて若干低いんです。ぜひ、単に体力を高めるというだけではなくて、子供たちがやはりすくすくと育って、生きる力を身につけてもらうためには、やはり家の中に閉じ籠もって、スマートフォンにかじりつくのではなくて、スマホよりももっと楽しい世界が神戸にはあるんだということを、保護者の皆さんも含めて理解をしてもらって、そういう機会を大いに活用していただいて、コベカツも、放課後にできるだけ豊かな時間を仲間と一緒に過ごしてもらう。要するに自分に何が向いているのかということを見つけてもらう、それがサッカーなのかテニスなのか野球なのか、あるいは伝統的な部活とはまた違うような分野、釣りでもいいかもしれません、山歩きでもいいかもしれません、新しいタイプのスポーツでもいいかもしれません。もちろんブラスバンドや、楽器に親しむということもいいかもしれません。とにかく、そういうようにして実際に体を動かし、仲間たちとフェースツーフェースで豊かな時間を過ごすことができる。それがすなわち成長環境なんですね。このことは、例えば何かを無料にします、現金を配りますということではない、それも大事ですよ。そのことも大事だけれども、そういうような経済的負担を軽減するということと相まって、みんなが力を合わせて、神戸ですくすくと子供が育つことができる環境というものを、我々はかなりつくり上げることができてきた。これをさらに前に進める、進化させる。これが神戸の子育て環境の基本的な考え方です。
記者:
ありがとうございます。もう1点お伺いしたいんですが、六甲山・摩耶山の整備、国際化とかに向けてロープウェーの計画など、前向きな取組も多く盛り込まれておりますが、一方で、去年は登山道で遭難された方がいらっしゃったりとか、民家でしたけども、林野火災につながりかねない火事というのも今年に入ってありました。市長としても、このにぎわい創出と並行して、山の安全・安心、どのように取り組んでいきたいか、お考えを聞かせいただけますでしょうか。
久元市長:
山の安全を確保することは非常に大事で、だからこそ登山道の整備をしっかりやると。これは神戸の六甲山系は崩れやすいので、全部追いつかない面もありますけれども、崩れたところはできるだけ修復するということだと思います。同時に、神戸の山を完全に誰でも歩きやすいようにするということはできないと思いますし、そうすることがいいのかというのは議論が必要です。典型的には、今日か昨日か、新聞にも出ていた「バリ山行」、あれは松永K三蔵さんでしたっけ、お名前、誰か知ってます? 何賞作家でしたか。
職員:
芥川賞です。
久元市長:
芥川賞作家の。上の名前は何ていう名前でしたっけ。
職員:
松永。
久元市長:
松永さんね、松永K三蔵さんの「バリ山行」、私も読みました。あの世界はそれ自体魅力的ですよね、あれは危険ですよね、あれはなくせないですね。そういうことを考えたら、安全に登山をしていくということと、それから山を楽しむということとは二律背反のところがあるということは事実です。ただ、そういうことも考えながら神戸市の消防局が、相当訓練された隊員の皆さんが遭難された方の救出・救助にも当たる。頻繁ではありませんけれども、ヘリコプターによる救出も体制はできていますから、そういう体制をしっかり取っていくということも相まって対応していくということです。
山上の火事の問題は、山上における消防体制を取れていたということで、そこは住民の皆さんとよく連携・協働をして、常備消防としての神戸市の消防局がしっかり対応していく、そういう体制を強化していくということだろうと思います。
記者:
ちょっと話戻って、「3つの再生」のことで二、三点だけお聞かせください。今回、森林・里山の再生、「3つの再生」の1つで打ち出されたんですけれども、この森林・里山の前提となる荒廃ですね。これについてもやはり阪神・淡路大震災による課題だというふうな受け止めをされているんでしょうか。
久元市長:
私はそうは思わないです。阪神・淡路大震災によって財政対応力が落ちたということは事実、そこの影響はあらゆる政策に及んだと思うんですが、神戸の里山の再生というのは、もっと前から進んできていました。大体、1964年の東京オリンピックの頃ぐらいが1つの転機だったと思います。それ以前は、神戸市の農村地域の間でも、上がれる人は山に入って薪を取ったり、薪を取ったり、それを日常生活の中で使っていた。循環型の社会が、ずっと長い間続いてきた循環型の社会というのが農村地域にあるようで、これは神戸だけではありませんけれども、続いてきた。それが急速に変わっていったわけです。ですから、これは震災による影響ではなくて、その前から起きてきた。それが数十年放置されてきたということです。これが、そこに近年、目を向けられるようになった。これに関心を持っていただいている皆さんも増えてきた。これ以降、より強力に政策として前に進めようと。都心の再生や既成市街地、ニュータウンの再生と関連づけながらこの森林・里山の再生ということをやっていこう、そこに多くの方々に参加してもらうという考え方です。
記者:
今回、「3つの再生」という言い方がすごい何か分かりやすいなと思ったんですけれども、特に最後の森林・里山の再生については、これはいつから温めていらっしゃったのかなというのを伺いたいんですが。空港国際化が決まってからぐらいからこういうことをやろうと思っていらっしゃったんでしょうか。
久元市長:
いや、もう数年前から庁内でも大分議論をして、それから、繰り返しになりますけど、こういう活動に関心を持っている方はたくさんいらっしゃるんです。増えてきているんです。もともと、例えば六甲山にブナを植える会だとか、生物多様性という言葉が使われる前から環境保全、自然環境を大切にするという活動をされる方はそれなりにいらっしゃいました。これが、関心が高まっていますね。例えば、ここ1年ぐらいの間に、新聞の広告を見ても、生物多様性とか、あるいは森林の再生とか、森をつくるとか、こういう広告というのはすごく増えていますよね。これは非常に大きなうねりになってきているというふうに思います。ですから、これは決して特異な取組ではなくて、繰り返しになりますが、グローバル社会でも、国際的に見ても大きな潮流になっているし、企業の社会貢献という面でもこのことが非常に大きな着眼点になってきているというふうに思います。
記者:
最後に1つなんですけれども、市長は何度もおっしゃられていたように、取組としては、中長期的な視点で取り組まれるものだということなんですけれども、とはいえ、市長として、数ある森林関連の施策で、まずどこで芽を出したいかというか、何かこういうところで成果を期待したいなと思っている分野とか特にあれば伺えればと思います。
久元市長:
例えば、今まで鬱蒼としていた林が、森が明るくなったと。植生の遷移によって、昔は人々が薪を取り、下草を刈り、枝を刈り、それを使っていたから明るい森になっていた。それが放置されて暗い森になっている。これが少しでも明るい森になるということは、「ああ、いい光景が広がったな」というふうに思っていただける面があるかもしれませんね。
それから、そのことと関連づけられて、土壌をしっかり考えないといけないんですけれども、そういう樹木を都心に移植する。そうすると木陰ができる。木陰ができて、その下は、かんかん照りのアスファルトではなくて、御影高校の子供たちが提案してくれたような木材チップだとか竹チップだとかが植えられた、そこは今までのアスファルトに比べて地表温度が低くなりますね。舗装を変えることによって舗装の表面の温度が低くなる、木陰ができることによってさらに低くなる。こういうような木陰がたくさん生まれるということは、ほっとする空間になるだろう。異常高温のときに、人が全然、人影が見られなくなるような姿ではなくて、そういう木陰の中に憩う人たちがいたり、ミストを感じる子供たちがいたり、東遊園地で見られるように水遊びをする子供たちがいて、水遊びに飽きたら木陰に入ってひとときを過ごすとか、そこで絵本を開いたりするという光景が生まれればすてきではないかなというふうに思う人たちが増えてくれたらとてもありがたいことですね。
記者:
すみません、資料に記載がない部分でちょっと恐縮なんですが、児童虐待の防止対策についてお伺いできれば幸いです。
1月に西区の事件で調査報告書が第三者委員会のほうから……。この質問は後のほうがいいですか。
司会:
予算関係を先に一通りしてから、その後でもよろしいですか。
記者:
一応、予算で2,000万円ぐらい今回計上されていると思うんですけど、県警との連絡共有みたいなところで。それで今後どういう体制をつくっていくのが望ましいと考えられているかというのだけ聞ければありがたいです。
久元市長:
西区の事案で報告書が出され、そしてこの検証委員会、これについての報告が出され、その中の項目については、しっかりとこれを実施していこう。そういう中で、大事な項目としては情報共有があります。この情報共有は、神戸市の中での各機関の情報共有、例えば区役所と児童相談所の情報共有もありますが、警察とのリアルタイムでの情報共有をやっていこう、情報共有システムを構築するというこのシステムに神戸市も参加をするということで、そのために必要な予算、これを令和7年度予算で計上し、これを令和8年度に稼働させる、そういう内容です。
記者:
すみません、ちょっと1点、森の再生のところなんですけど、これ、主に伺っていた話だと、六甲山とか環境の改善というところが大きいのかなと思うんですけども、神戸市さんはスタートアップの支援とかも積極的にやっていらっしゃって、ひいては、この森の再生という森林の分野での新たなビジネス創出とか、そういうところにつなげていくという意味とかも込められていらっしゃるんでしょうか。
久元市長:
大変期待しております。森林の再生についても、スタートアップの活動が最近盛んになっていますから、そういう分野にスタートアップの皆さんに参加をしていただくことは大変期待しております。スタートアップとしては、神戸市としては新たなファンドもつくりたいと思っていますから、そのファンドの投資対象としては、こういう森林の再生なども考えていきたいと思います。
森林の再生というと山の中というイメージがあるんですけども、森林・里山ですよね。この森林・里山は、これは雑木林と田畑と、それから神社仏閣だとか、茅葺などの民家が一体となった世界です。神戸が「500 Startups」で応援をしてきた、耕作放棄地を、一目瞭然にどこに耕作放棄地があるのか、その状態はどうなのかということが分かるスタートアップ、これは神戸市が支援をしたわけですけれども、これはビジネスになっていますね。これは1つのモデルケースですけれども、これはパイオニア的なスタートアップだったと思いますけれども、こういうようなスタートアップの皆さんが、神戸が森林、「森の未来都市」プロジェクトを神戸でやっていこうと。そこでいろんな取組をしていただきたい。神戸はそういう実験フィールドを提供するということで、そういう今おっしゃったような森林再生あるいは里山再生、耕作放棄地再生のスタートアップがどんどん生まれていくような都市、つまり、これは森林・里山再生ですよね。「森の未来都市神戸」のプロジェクトによって、この神戸でそういう社会貢献に関心があるスタートアップの皆さんがビジネスを展開してもらえるような都市を目指す。そのために必要な支援というものをしっかりとやっていきたいというふうに思います。
記者:
神戸市債を活用した、主に投資的経費の財源としてということだと思うんですが、そこについては、しばらく、ここ数年よりももうちょっと前ぐらいから、そうした活用できる余地があるというふうにおっしゃっていたかと思うんですが、今、財政は非常に健全な状況であるというふうに2つの指標を使ってお示しいただいているんですが、どの程度まで悪化を許容できるのかというようなところに何か目安となるような考え方はあるのでしょうかというのが1つです。
あと、もう1つありまして、昨年末に分かっていたこととは言いながらも、今回、臨時財政対策債の発行がゼロということに関して何かコメントがありましたら頂戴できればと思います。よろしくお願いします。
久元市長:
まず、これはちょっと財政当局から答えてもらったらいいと思いますけど、将来負担比率が何%以上になれば起債の発行が許可制になる、あるいは何%以上になったら起債の制限ができなくなる、発行ができなくなる、実質公債費比率についても同じような制限があるんですよね。まずそれが。ただ、それを大幅に神戸市は下回っているということです。まずそこの許容範囲、そこの中にいるということが最低求められています。
職員:
行財政局です。
まず、実質公債費比率と将来負担比率につきまして、それぞれ国のほうの基準で早期健全化基準というもの、これは、この基準を超えますと早期に財政再建に取り組む必要があるということでございまして、あともう1つ、財政再生基準というものがございます。こちらのほうも国の関与の下、財政再建に取り組むという基準でございまして、実質公債費比率につきましては、早期健全化基準が25%、それから財政再生基準が35%という水準になってございます。本市の場合は、見て取れますように4.9%ということになっていまして、当然ながらそこの水準には及んでないということでございます。また、将来負担比率は早期健全化基準だけですけれども、こちらは400%という水準でございますので、はるかに低い水準というふうになってございます。
久元市長:
まずそこに行くのは論外なんですよ。論外なんです。そしたら、そこの間で現実的にどの辺まで許容できるのかという御質問の趣旨だと思うんですが、それはなかなか言い難いですね。例えば、よその都市のことを言うのはあれですけど、京都はかなり高いですよね。ですから、別にこういう神戸よりも高いところでも立派にしっかりとした財政運営がなされ、いろんなまちづくりが行われているわけですから、だから、どこまでこれが悪化しても大丈夫なのかというのは一概には言えないです。
ただし、少なくとも言えることは、神戸市は戦前から日本を代表する大都市ですけれども、財政力ということから見たときには決して強いとは言えないんですよね。財政力指数ということから見ても決して高いほうではありません、財政力指数は。それから、財政力というのは1人当たりの税収の額と大体相関するんですけれども、1人当たりの税収額というのも決して高くはないんですよ、類似の都市から見ても。福岡や川崎に比べたら、横浜、川崎から比べたら相当低い、1人当たりの税収額が低い。
神戸市は、そういうことから見れば決して財政構造が強固ではないんですね。同時に、これから扶助費がどんどん増えていくということを考えれば、やっぱり財政運営というのは慎重に行わなければいけない。積極的なまちづくりは進めますけれども、そこはやはり節度を持った投資規模ということを考えないといけないし、これからもやはり行政改革というのはしっかり行わなければいけないというふうに思います。
記者:
指標としてはあまり悪くしたくないというふうにはお考えになっているということですか。
久元市長:
あまり悪くしたくありません。この平均ですよね。この平均よりもこれを上回るような状況にはしないほうがいいのではないかというふうに思っています。
記者:
分かりました。
あと、臨財債についてお伺いします。
久元市長:
臨財債については、これは国の制度で決まってくるわけで、我々はもともと地方六団体みんなそうですけれども、臨時財政対策債は廃止していただきたいというふうに思っていましたから、これは大変よかったというふうに思っています。
1つには、全体的に地方税についても堅調な状況に来年度はあると、そう見込まれるということと、それから、やはり地方財政全体についての健全化の努力ということが行われてきたということ。そのことによって臨財債の発行がゼロになったということだと思います。
記者:
高校生の通学定期券の部分で伺います。昨年の予算のときに、大阪の無償化を経て、兵庫県にお願いする上でぎりぎりの、神戸市としてやれることとして始めた施策が、今回大幅拡充ということだと思うんですが、その狙い、昨年も結構ぎりぎりのところまでやったというところに対して、今年またさらにそれを大幅拡充したそこの狙いについてと、今回これをさらに攻めたことによって兵庫県に何かしら、より要望していくだとかそういうお考え含めてありましたら教えてください。
久元市長:
これは、大阪府が高校の所得制限を設けることなく、実質的には、63万円を超える数字は別として、大阪府がそういう措置に段階的に踏み切ったということで、兵庫県と非常に大きな差ができたわけですから、これは兵庫県に対応してもらわないと困るわけですね。しかし、兵庫県はなかなか難しいという返事だったので、そうであれば、基礎自治体として何ができるのか。これも庁内で本当に何回も議論して進めて、これは高校になったときに非常に増えるのが通学費の負担で、これをゼロにしようと。特に我々は基礎自治体ですから、神戸市内の高校をしっかり守る。県立、市立、私立、様々な多様な高校が神戸に存在をするということが神戸の豊かな教育環境をつくっている、あるいは、まちのにぎわいとか活力の源泉になっている。だから、神戸市内の高校をしっかり守らなければいけない。経済的負担を、つまり、大阪と非常に大きな差がある。これは本来、兵庫県がやらないといけないわけですけど、それを兵庫県ができないと言うから、やむにやまれず神戸市がやっぱり対応しなければいけないということでこれに踏み切ったわけです。
ですから、そういう2つの目的から考えれば、我々は基礎自治体ですから、これは市内の高校生が市内の高校に通う場合の政策をどうつくるのかというのは我々のミッションなんですよね。我々は県ではありませんから。だから、これを市内を対象につくると。市外については1万2,000円を超える部分の半額を助成にする、これは前から行ってきたわけですから、そこは我々のミッションの対象ではないという考え方で、それを踏襲したわけですね、令和6年度に。しかし、やっぱり市民の皆さんからは、不公平だと、差があるのはおかしいという意見が結構ありました。だからそこは、市内と市外とを全く同じにするというのは我々の任を超えます。ですからその差は維持しますけれども、これも大幅に拡充することにしたということですね。ですから、これは引き続き兵庫県にはしっかり検討をしていただきたいと。
さっきも申し上げましたけれども、特に今、国のほうで、与野党間で議論が行われますが、その最終形がどういう姿になるのか、間もなくそんなに時間をかけずに決着すると見込まれますから、その結果、大阪府と兵庫県との間にどういう格差が残るのか、これを考えるのは兵庫県の責任ですよ。それをしっかり考えてもらいたいということです。
記者:
それを、兵庫県に向けて市長自ら何かしらアプローチというか、お伝えをしていくようなことは考えていらっしゃいますか。
久元市長:
この前、説明がなかったのは大変残念でしたけど、検討の場をつくっていただくということでしたから、それを見守りたいと思います。
記者:
先ほどの「森の未来都市神戸」に関連してもう少しお伺いします。先ほどのお話の中で、森林関連のスタートアップのビジネスも展開していくまちを目指すというお言葉もありましたけども、グローバル社会の中で名誉ある地位とか価値というのは、例えばですけど、神戸空港の国際化に絡めて森林関連で国際的なビジネスが神戸から発展していくことを目指すのか、あるいは住んでいる方の幸福度というか、満足度を上げていくとかなのか、海外の企業が進出したり、進出先として選ぶということを念頭に置いているのか、どういうことなのかというのを、すいません、もう少し具体的にお伺いできますか。
久元市長:
森林再生ということが、グローバル価値を持ってきているということです。そういう都市を目指すことが、グローバル社会の中で名誉ある地位を獲得することにつながるということだと思うんですよね。そういうような価値というものをどれだけ多くの方に理解していただけるものかということだと思いますね。
同時に、神戸に豊かな森林がある、豊かな里山があることは、神戸の大きな魅力になっているということも事実です。例えば、残念ながらコロナで撤退することになりましたけれども、マッキンゼーが日本で初めて大規模な研修施設をつくってくれました。これは新神戸駅のすぐ近くにつくってくれたんですね。これは何に着目したかというと、すぐ近くに山がうかがえます。すぐ近くに緑滴る山から清流が流れ、すぐ歩けば布引の滝があると、こういうところに着目してくれたものです。
最近、ロンドンに本拠があるインターナショナルスクールが神戸に立地しました。まずは六甲アイランドで教育を始めて、ゆくゆくは六甲山脈に行くことが楽しみだと。この六甲山の山上の自然環境、緑豊かな自然環境の中で、子供たちがゆっくりと、ゆったりと学ぶことができる環境、こういうものが神戸にはあるわけですよね。ところが、もう繰り返しませんが、様々な課題があって荒廃をしてきている、これを再生するという取組をみんなが力を合わせてやることができる都市であるということが、そういう企業の誘致や、あるいはインターナショナルスクール、学術研究の面で、教育研究ということから見たときにプラスの効果があると思うんですね。
しかし、そのこと、その1つ1つのことというよりも、もっとトータルにこういう取組をすることが神戸全体のブランド価値を高めるということについて理解していただけるかどうか、そこはたくさんの皆さんとこういう方向性について議論を重ねていくということが大事だと思います。
質疑応答(発表項目以外)
記者:
すいません、1点だけ。神戸市出身で拉致の被害に遭われた有本恵子さんの父親の明弘さんが亡くなっているという訃報が報じられました。そのことについて、神戸市出身の方で、神戸市在住の方というところで、市長からコメントを改めていただけないでしょうか。お願いします。
久元市長:
神戸出身の有本恵子さんがもう大分前に行方不明になって、北朝鮮に拉致されたことは確実だとされていますね。
そもそも、拉致被害というのは絶対に許してはいけないということだと思うんですよね。そして政府も努力をされて、2002年だったでしょうか、5名の方が帰還された。ただ、その後、それ以外の方が帰還されていない。本当に御家族の皆さん、帰還を待ち望んでこられたと思うんですけれども、その中の1人がこの有本恵子さんの御家族で、有本明弘さんがそれを待ち望んでおられたわけですけれども、再会がかなうことなく逝去されたということは私も残念だと思います。大変、御心中はいかばかりかと。どういう思いを最期までお持ちになっておられたのか。ぜひ娘に会いたいということを熱望されていたと思うんですけど、その願いがかなわなかったということは大変悲しいことだと思います。
やはりこの問題は国によって解決されることが唯一の道ですから、政府においてこの拉致問題ということを、大変困難な問題であるとは思いますけれども、ぜひ全力で解決をしていただくことを求めたいと思います。
記者:
ちょっと追加でお伺いしたいんですが、1月に提出された西区の虐待事案に関する報告書の受止めを改めてお伺いしたいというのが1つと、今年度の組織改正等で、また西区だったりとか人口が多い区役所の担当職員が増員されますとか、そういった対応を進めていかれると思うんですが、報告書の内容に照らすと、もう少し継続的な対応というのが今後も必要になっていくのかなというふうに個人的には思いました。市長として今後、どういった体制をつくっていかれるのが望ましいかというところで、お考えがあればお聞かせください。
久元市長:
まず、この検証委員会の皆さん、これ、5回にわたって開催していただいて、個別にも様々な御意見をいただいたり、あるいは調査にも関わっていただいたということで、改めて、大変詳細で具体的な報告書を取りまとめていただいたことに感謝申し上げたいと思います。
大きく6点にわたって提言がなされているわけですが、それぞれについて神戸市としては対応したい。例えば情報共有ですよね。情報共有も、区役所と児童相談所、それから区役所間で情報共有するということで、児童相談システムを相互に閲覧できるようにシステムを変えるということなど、それから、区役所と保育所との間の連絡会も定期的に開催するというようなことですよね。それから、先ほど申し上げましたけれども、警察との間のリアルタイムでの情報提供というようなことをやっていくと。それから、体制面の強化としては、児童相談所の体制強化ということで、(令和6年度組織改正で)課長1名係長2名を増員した。それから、(令和7年度組織改正で)区役所における体制の強化、(児童)人口が多い東灘区、垂水区、西区での虐待対応職員を1人増員すると、こういうような対応。それから、こども家庭局にも養育支援担当の係長を新設する、こういう対応をしっかりやっていくということですね。
同時に、体制の強化だけではなくて、職員の皆さん、相当専門的な知識や経験を持った職員がたくさん神戸市にはいるわけですけれども、全体としての底上げを図っていくということからいうと、研修の強化ということは非常に重要なので、そういう取組も行っていくということを、やはり継続的にやっていきたいと思います。
記者:
そしたら、1点だけ追加で。
例えば人口が多い自治体の区役所の職員さんだったりとかというのは、今後も増員を続けていくのかどうかというところは。
久元市長:
組織体制については、各年度、例えば今回、体制を強化したところでどういう効果があったのかとか、ほかのところについては課題があるのかということは、新年度に入った仕事の状況を見ながら考えていきたいと思います。
記者:
すいません、全く関係ない質問で恐縮なんですけども、先週の13日、村上総務大臣が衆院の総務委員会のほうで、今世紀末に人口が半減するという推計を踏まえて、現在が1,700の自治体は300から400の市で済む、極端なことを言えば県庁も要らないというふうな発言をされました。先ほど市長からも人口減少に関しての発言がありましたが、今後、人口が減少していく中で現在の自治体のシステムを維持できるのかという指摘もあると思いますが、この発言に対して何か受け止めがありましたらお聞かせください。
久元市長:
これは今世紀末なんですか、村上大臣のそれは。
記者:
はい。
久元市長:
今世紀末?
記者:
はい。
久元市長:
今世紀末ということなので、相当先のことですよね。あと70年から80年か先のことですが、それまでに間違いなく起きることは、日本の人口が減り続けるということですね。まず間違いない。そういうことを考えると、その70年か80年先に日本の人口が減り続けるということは、自治体の職員をもう採用できなくなるということですね。ですから、今の市町村の体制が維持できるかどうかということは分からない。
それから、2層制ということが一応前提になっているけれども、2層制が維持できるのかどうか、あるいはそれが適切かどうかということは分からないということをおっしゃったのだろうと思います。つまりそれは、これから急激に人口が減っていく中での、村上総務大臣としての、あるいは総務省としての危機感を開陳されたというふうに受け止めております。
記者:
ちょっと発言の中で、県庁は全部要らないと、将来的には基礎的自治体の市と国が直接やり取りをしたほうがよいんじゃないかというような趣旨の発言もされていますが、市長として、地方における都道府県の役割ですとか在り方について、何か意見がありましたらお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
久元市長:
まず、今のお話は、70年から80年先の話ということであれば、それはもう相当先の話になって、そこは間違いなく人口は減り続けるわけですし、職員ももう今の体制では対応できないわけですから、その時点で、1層制ということについては、これは議論としてあり得るだろうと思います。現実に諸外国の制度を見ても、1層制を取っているというのも現実にはありますから、あり得るだろうと思います。近未来でいうと、今の2層制ですよね、広域自治体と基礎自治体の2層制をすぐに解消するというのは、これはやっぱり無理です。広域自治体は広域自治体としての役割をしっかり果たしていただくことが必要だと思います。
基本的な地方自治制度の構造というのは2層制ですけれども、個別に見ると、これは、基礎自治体、特に政令指定都市のような大規模な自治体が、道府県を介することなく国と直接連携するほうが効率的な場合というのはあります、経験もいたしましたが。典型的に言うと、コロナのときの情報共有ですよね。例えば患者の感染者の確認とか、それから、特に困ったのはワクチン接種ですね。ワクチンの接種を市が県に報告し、県が厚生労働省に報告し、厚生労働省が指定都市の分も含めて県に配分して、そしてそれがまた指定都市にやってくると。非常に非効率、時間もかかりました。それから、医療機関に対する交付金がありましたけれども、これも、指定都市の分を指定都市に任せてもらって、県は指定都市以外のところを担当してもらったほうがよっぽど早かったのに、実際に申請してから交付されるまで物すごい長い時間がかかったんですね。こんなことはやっぱり改めてもらうほうがいいと思いますね。
そういう個別の事務については、県経由ではなくて、国の各部署と指定都市とが直接やり取りをする、情報を共有する、交付金などについては直接交付をする、こういうやり方に改めていただくべき個別行政分野というのはかなりたくさんあると思います。
―― 了 ――
動画ソフトウェアのダウンロード
このページは接続環境によって、映像・音声などがみだれたり、スムーズな視聴ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
よく見られているページ
- 臨時会見 2021年(令和3年)2月3日
- 臨時会見 2021年(令和3年)2月3日
- 定例会見 2022年(令和4年)9月7日
- 定例会見 2023年4月14日
- 定例会見 2023年9月28日
- 定例会見 2023年10月12日
- 定例会見 2023年10月27日
- 定例会見 2023年11月15日
- 定例会見 2023年11月24日
- 臨時会見 2023年12月5日
- 定例会見 2023年12月14日
- 臨時会見 2023年12月22日
- 定例会見 2023年12月26日
- 定例会見 2024年1月11日
- 定例会見 2024年1月24日
- 定例会見 2024年2月14日
- 定例会見 2024年3月14日
- 臨時会見 2024年3月27日
- 定例会見 2024年3月28日
- 定例会見 2024年4月12日
- 定例会見 2024年4月26日
- 定例会見 2024年5月8日
- 定例会見 2024年5月23日
- 定例会見 2024年6月13日
- 定例会見 2024年6月27日
- 定例会見 2024年7月11日
- 定例会見 2024年7月26日
- 定例会見 2024年8月22日
- 定例会見 2024年9月12日
- 臨時会見 2024年9月24日
- 定例会見 2024年9月26日
- 定例会見 2024年10月10日
- 定例会見 2024年10月25日
- 定例会見 2024年11月14日
- 定例会見 2024年11月25日
- 臨時会見 2024年12月4日
- 定例会見 2024年12月12日
- 定例会見 2024年12月26日
- 定例会見 2025年1月10日
- 定例会見 2025年1月22日
- 臨時会見2025年2月4日(1)
- 臨時会見2025年2月4日(2)
- 臨時会見2025年2月5日
- 定例会見 2025年2月17日
- 定例会見 2025年3月14日
- 臨時会見2025年3月25日
- 定例会見 2025年3月26日
- 定例会見 2025年4月10日
- 定例会見 2025年4月22日
- 定例会見 2025年5月9日
- 定例会見 2025年5月21日
- 定例会見 2025年6月12日
- 臨時会見 2025年6月18 日
- 定例会見 2025年6月27日
- 定例会見 2025年7月10日
- 定例会見 2025年7月29日
- 定例会見 2025年8月27日
- 定例会見 2025年9月11日