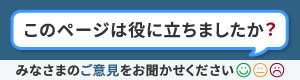ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 組織・人事 > 副市長・教育長・幹部紹介 > 教育長から市民のみなさまへ
教育長から市民のみなさまへ
最終更新日:2025年5月2日
ページID:75016
ここから本文です。
教育長 福本 靖(ふくもと やすし)
子どもが主役の授業改善の流れを作る

経歴はこちら
神戸市で生まれ、大学まで市内で学び、中学校の社会科教員として神戸市に採用されました。教育委員会事務局や中学校校長を経験し、2022年に定年退職となりました。2024年から教育長を務めています。
学びの不易流行
学習指導要領の変遷をみると、「心豊かな人間」「生きる力」などの理念が書かれています。2024年4月に、神戸市教育委員会は第4期神戸市教育振興計画において、目指す人間像として「心豊かに たくましく生きる人間」を掲げました。時代が変わろうとも、不易流行の不易の部分は、教育の本質として大切にしたい思いが込められています。
一方で、少子高齢化や人口減少、共働き世帯の増加、急速な技術革新の進展やグローバル化など、社会状況の変化はますます激しさを増しています。学校を取り巻く環境も、その変化は著しいものがあります。急激な時代の変化に対応するためには、今まで学校が必要と考えて疑わなかったことに対しても、これからは改革を進めていくことが必要な場面もあるでしょう。
子供が主役のこれからの学び
これからの時代において必要となる、問題発見・課題解決能力や創造力、コミュニケーション能力、ICTの適正な利用活用による情報活用能力を育むとともに、異文化や多様な背景を持つ人々への理解を深めることも大切なことです。学ぶとは、ある意味において離陸を意味するようにも感じます。今までいた地上から、大空に向かい飛び立つことで、見えなかった風景が見えるようになります。子供たちが自ら学びたいという、内側から湧き出る思いを学校は大切にしていきたいと思います。そのためには、教員が最も力を注ぐ対象は、日々の授業となります。もちろん今も教員は、授業改善に様々な工夫をしています。しかし、どうしてもその日の授業の振り返りや、改善策に時間を割くことが難しかった一面があったことも事実です。子供が主役となる学びを実現するためには、教員が教材研究や授業研究をしっかりできる環境を、制度としてバックアップする必要があります。
働き方の転換
自身が教員になった頃は、毎日遅くまで学校に残り、教材研究や部活動指導をしていました。土日も練習試合や公式戦引率などで、家にいる時間は少なかったように思います。周りの教員も、同じような毎日を過ごしていました。もちろん、その時代はそのようにすることで、教育効果があった側面も理解しています。しかし、時代も変わりコロナ禍も経て、働き方に対する認識は変化しました。8時から17時までの勤務時間の中で最も効果的な教育成果が得られるように工夫することが、持続可能な教員人生を可能とします。
日々の授業改善の積み重ねを
8時から17時までの勤務時間は、そのほとんどが授業です。そう考えると、その中心である授業を、教員同士が切磋琢磨して良い授業としていくことこそが、生徒の学びを深める根本となります。教えることは教えられることであり、日々の授業の中で子供から学ぶことができる教員が、授業の中から常に新しい意味を汲み出すことができます。そのような研鑽を積んだ教員が発する言葉からは、子供たちがたえず驚きを感じることができるでしょう。それは子供たちの学ぶ喜びともなり、深い学びへとつながっていきます。授業の深化こそが、すべての子供たちのなかに潜んでいる、最善の可能性を引き出す原動力となるでしょう。神戸市では、これからも教員の授業改善を全力で支援し、深い学びの喜びを創造していきます。
よく見られているページ
- 市会事務局長の紹介ページ
- 監査事務局長 兼 人事委員会事務局長の紹介ページ
- 選挙管理委員会事務局長の紹介ページ
- 交通事業管理者の紹介ページ
- 水道事業管理者の紹介ページ
- 消防局長の紹介ページ
- 西区長(経歴)
- 垂水区長(経歴)
- 健康局長の紹介ページ
- 北区長(経歴)
- 兵庫区長(経歴)
- 中央区長(経歴)
- 灘区長(経歴)
- 東灘区長(経歴)
- 港湾局長の紹介ページ
- 建築住宅局長の紹介ページ
- 都市局長の紹介ページ
- 建設局長の紹介ページ
- 環境局長の紹介ページ
- こども家庭局長の紹介ページ
- 福祉局長の紹介ページ
- 企画調整局長の紹介ページ
- 教育長
- 副市長
- 経済観光局長の紹介ページ
- 理事兼都市局都心再整備本部長の紹介ページ
- 副市長から市民のみなさまへ
- 副市長から市民のみなさまへ
- 副市長から市民のみなさまへ
- 教育長から市民のみなさまへ
- 危機管理監兼危機管理局長の紹介ページ
- 会計室長の紹介ページ
- 地域協働局長の紹介ページ
- 行財政局長の紹介ページ
- 灘区長(経歴)
- 北神区役所北神担当区長(経歴)
- 長田区長(経歴)
- 須磨区長(経歴)
- 教育委員会事務局長兼教育次長の紹介ページ
- 文化スポーツ局長の紹介ページ