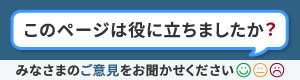建築基準法の道路と手続き
最終更新日:2025年6月30日
ページID:7438
ここから本文です。
道路種別の調べ方
- 建築基準法の道路の種別は、インターネットか窓口で調べることができます。
- インターネットと窓口で、公開している道路種別情報は同じです。
- 道路法の道路を調べる場合は、「公道か私道か調べる」のページをご確認ください。
道路種別と手続き
| 建築基準法 第42条 |
道路の種類・名称など | 主な問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 1項1号 | 【道路法】 道路法による幅員4メートル以上の道路 |
<公道・私道、道路台帳平面図>
|
| 1項2号 | 【開発等道路】 都市計画法、土地区画整理法等による幅員4メートル以上の道路 |
<開発許可>
|
| 1項3号 | 【既存私道】 基準時(注)に現に存在する幅員4メートル以上の道路 |
|
| 1項4号 | 【事業予定道路】 道路法、都市計画法、土地区画整理法等の事業計画のある道路のうち特定行政庁(市長)が指定した幅員4メートル以上の道路 |
|
| 1項5号 | 【位置指定道路】 政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁(市長)からその位置の指定を受けた幅員4メートル以上の道路 |
|
| 2項 | 【みなし道路】 基準時(注)より存在し、かつ幅員や建ち並びに関する一定の要件を満たし特定行政庁(市長)が指定した幅員4メートル未満の道 ※基準時(注)の道路中心線から2メートル後退(対側が川、線路敷の場合は一方後退4メートル) ※2項道路拡幅整備届出書の提出をお願い |
|
| 3項 | 【水平距離指定】 法42条2項道路のうち、特定行政庁(市長)から水平距離(道路の中心線から道路境界線までの距離)の指定を受けたもの ※基準時(注)の道路中心線から指定された水平距離(1.35~2メートル)後退 |
|
| 建築基準法の道路でない | 上記に該当しないもの ※建築基準法上の道路に接道しない敷地で建築行為を行う場合は、確認申請の前に許可が必要 |
|
| 未判定 | 現地に道の形態があるが道路種別が示されていないもの |
|
(注)基準時は、以下の地域を除き、1950(昭和25)年11月23日(建築基準法施行日)
- 北区道場町、八多町、大沢町 1951(昭和26)年7月1日(都市計画区域編入日)
- 北区長尾町 1956(昭和31)年11月10日(都市計画区域編入日)
- 北区淡河町 1958(昭和33)年6月16日(都市計画区域編入日)
私道の廃止
私道であっても建築基準法の道路は変更・廃止の制限があります。建築安全課の4番窓口で相談ください。
よくある質問
窓口・問い合わせ
651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30 三宮国際ビル5階
神戸市建築住宅局建築指導部建築安全課(④窓口)
建築基準法の道路についての質問は、問合せフォームをご利用ください。
よく見られているページ
- 建築基準法の道路と手続き
- 高度地区
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)
- 地区計画の条例による制限
- 特別用途地区「文教地区」
- 角敷地等の建ぺい率緩和
- 建築協定
- 指定建築物制度
- 建築紛争を防ぐために
- 接道許可
- 総合設計制度
- マンション建替型総合設計制度
- 一団地認定及び連担建築物設計制度
- 仮設建築物の許可
- 仮使用・安全計画
- その他の許可及び認定
- 近隣住環境計画制度
- 防災計画書
- 駐車施設の附置義務と届出
- 路外駐車場の設置届出
- 大規模な駐車施設等の制限
- 建築物への自動車公害の防止措置
- 緑化計画届
- CASBEE神戸の届出
- 建築物省エネ法の適合義務
- 建築物省エネ法による認定
- バリアフリー法の認定申請
- 低炭素建築物の認定申請
- 長期優良住宅の認定申請
- 確認申請の手続き
- 建築計画概要書を作成するにあたって
- 建築物の中間検査
- 完了検査
- 定期報告制度(建築物・指定建築設備・防火設備・昇降機)
- 建築物等の事故への措置と届出
- 建築計画概要書等の閲覧・証明書発行
- がけ条例
- 建築物除却届
- 事前届出制度
- 定期報告(指定建築設備・防火設備)
- 既成都市区域の証明願
- 長期優良住宅型総合設計制度
- 「神戸市すまいの環境性能表示実施要綱」の一部改正